STRATEGY
【前編】生成AIで変革を加速せよ——パーソル各社の事業をアップデートするグループAI・DX本部の挑戦

パーソルグループ全体の共通業務基盤を担うパーソルホールディングス グループAI・DX本部 ビジネスITアーキテクト部が、生成AIをはじめとするテクノロジーを活用し業務プロセスの変革を加速させています。
中期経営計画の最終年を迎えた2025年4月、これまでの5室体制から11室体制へと組織を大幅に再編し、グループ各社と連携しながら業務の高度化を進めるなか、ビジネスITアーキテクト部は何を目指すのでしょうか。組織を率いる部長の木村に今後の展望と求める人物について聞きました。
グループAI・DX本部は「テクノロジーの力で顧客体験 / 従業員体験 / 事業を変革する」を組織のミッションに掲げ、AI時代の新たな「はたらく」の創造と労働集約モデルのアップデートを目指しています。そのなかで我々ビジネスITアーキテクト部は、パーソルグループ国内38社、約6万人の従業員が利用するグループ共通業務の基盤システムの改善やBPRの推進によるグループ全体の生産性の向上、さらにそこに蓄積されたデータの利活用を通して経営戦略に対して示唆を与えることをミッションとしています。
過去2年にわたり、パーソルグループの人事、財務、営業など、各業務を束ねるホールディングスの所轄部署と共に、グループ共通業務基盤の強化、改善に努めてきました。その一方で、ビジネスITアーキテクト部の自発的な提案が少なかったという反省点がありました。今後、我々の専門性として企画、運用両方の質を高めて中期経営計画の最終年の対応およびさらなる生産性向上への対応に向けて体制強化を図ったというのが、4月の組織改編の理由です。
具体的には、広範な業務領域をカバーし、急速に進化するAIを事業成長の力に変えるために、以前からグループ共通業務を支えてきたビジネスITアーキテクト部の機能を細分化し従来の5室から11室に増強しました。各室には業務に精通したメンバーを集め、専門性が高い組織をつくり権限を渡し、機動性を高めるためです。
ビジネスITアーキテクト部の機能は大きく3つに分けられます。ひとつ目が、各社の人事、財務、総務・購買、営業、コーポレート部門の業務をデジタルテクノロジーで革新するDX系の組織。こちらは新規の企画開発を担います。
ふたつ目が、各社の各部門に導入されている既存のシステムに磨きをかけるEX(Employee Experience)系の組織。こちらは既存システムの拡張開発や、保守・運用を担います。
最後がDX系、EX系組織にて担う企画やプロジェクト、サービス提供それぞれの質を向上したり、生成AIをはじめとするイノベーションに不可欠な最新テクノロジーの試行・支援各室に提供したりする共通系組織です。
今回実施した組織変更で全て完了ではなく、DX系・EX系・共通系組織を軸に、その時々で柔軟に変化していきたいと思っていますが、まずは今回の再編を通して以前にも増して企画提案を我々から仕掛けるとともに、着実なプロジェクト運営を実施し、生産性向上にコミットしてアカウンタビリティを果たしていきたいと思っています。
主だったプロジェクトを紹介すると、人事領域については、キャリアオーナーシップを支援する「CareerMill(キャリアミル)」や、社員のMBO・評価を行う「CareerPolaris(キャリアポラリス)」の機能拡張、財務領域については、財務会計システム「SAP」や管理会計システム「Tagetik」の導入、総務購買領域では購買システムの導入、稟議決裁等の各種領域をつなぐワークフローでは「ServiceNow」の導入等を行っていきます。また、各業務領域を支えるシステムの運用・保守の自動化等の高度化も図っていきます。
他にも、データ活用の観点ではグループ共通業務のデータが我々の組織にはたくさん集まっていますので、データカタログの導入や財務や営業系データの見える化・分析により、経営に示唆を与える取り組みも試行・拡張していく予定です。
これだけでもビジネスITアーキテクト部の守備範囲の広さをおわかりいただけると思います。これらの具体的な取り組みは、また別の記事にてご紹介できたらと思います。

現行の中期経営計画が満了する2026年3月に向けた総仕上げの年でもあり、さらなる生産性向上に向けて新たな企画を仕込んでいく年でもあります。
具体的には、中期経営計画の仕上げの観点で言うと、先ほどの各種プロジェクトの新規導入やグループ会社への展開です。達成状況的には計画の6~7割程度まで進んでいますが、これまでの初期導入を通して下地が整ってきた段階でもあるので、残り1年で十分にやり切れる範囲かと考えています。
さらなる生産性向上の観点でいくつかご紹介すると、パーソルグループは人材サービスの業界でもありますので、我々独自のタレントマネジメントのあり方を、先にもご紹介した「CareerMill(キャリアミル)」や「CareerPolaris(キャリアポラリス)」の連携・活用を通してパーソル独自で実現したり、提供するシステム全般について従業員が直感的かつ効率的に利用できる仕組みを導入したり、AIの活用による業務改善等に取り組んでいきたいと思っています。
すでに社内で「CHASSU(チャッス)」の愛称で親しまれているパーソル社内版GPT「PERSOL Chat Assistant」をはじめ、営業現場では生成AIによる商材レコメンド機能や情報収集機能を備えたWebアプリの「Genie(ジーニー)」や、社内向けにはAIチャットボットなど、グループ各社の各業務領域で生成AIの活用が広がっています。
本部名に「AI」が含まれる通り、本部として生成AIを事業成長のエンジンにしたいと考えておりますが、それはビジネスITアーキテクト部も変わりません。所掌範囲としているグループ共通業務には、生成AIにより業務効率が狙えるタスクが多く存在していると想定しております。今期から徐々に、その企画を我々自ら業務担当の方々に向けて提案を行い、さらなるグループ全体生産性向上を狙っていきたいと思っています。
企画立案の段階で、パーソルホールディングスの各CxOだけでなく、各社のトップやステークホルダー、現場ステークホルダー双方に対して、ホールディングスの各事業本部と共にしっかりと意志を伝えることを大切にしています。プロジェクトが動き出す前にボタンの掛け違いをなくし、考えに共感してもらわなければ大きな成果は残せません。熱意と誠意を持って接することを心がけています。
大きく2点あります。1点目は、先ほども申し上げた生成AIの活用です。事業拡大、業務効率化を拡大していくためには、生成AIの活用は必要不可欠なものだと思っていますので、その活用が常態化するよう、我々から変革のアプローチをし続けたいと思います。
2点目はデータ活用です。ビジネスITアーキテクト部が扱っている情報は、パーソルグループ内の人事、財務、営業などコーポレートの情報になり、膨大かつ多種多様になります。まだ、その活用は道半ばですが、経営や事業戦略への示唆が与えられるようにこれからの企画を加速させたいと思っています。

端的にいうと、変革への意志を持たれている方です。目の前の課題解決に情熱を傾けられる方、自発的に行動できる方を求めています。ただ、これだけ規模が大きな取り組みになると、ひとりでできることは限られるので、チームワークを大切にし、ご自身の知識や経験で周囲をインスパイアできる方、相互理解のための努力を惜しまない方であってほしいですね。
現在、ビジネスITアーキテクト部に在籍するメンバーの多くが事業会社のコーポレートIT出身者やSIer出身者で占められています。大規模なシステムが中心なので、少し難易度が高いと感じるかもしれませんが、パーソルには仲間同士支え合い、学び合う文化と、従業員の成長を後押しする各種制度が充実しており心配いりません。パーソルホールディングスのバックオフィス部門のみなさんはもちろん、グループ各社で事業を担う方々も変革に対して前向きですから、きっと力になってくれるはずです。システムの構想や企画立案、要件定義など、上流工程の経験があれば、すぐに活躍いただけると思います。
パーソルグループは現在、「テクノロジードリブンな人材サービス企業」を目指しておりIT投資に積極的です。また、テクノロジー人材に特化した人事制度も整備され始めており、安心してキャリア形成ができるでしょう。もし基幹業務を支えるコーポレートITに興味をお持ちであれば、パーソルホールディングスでのキャリアを検討してみてください。きっと有望な選択肢になるはずです。
取材・文=グレタケ 武田敏則
※所属組織および取材内容は2025年7月時点の情報です。
※略歴内の情報は2025年10月時点での内容です。

パーソルホールディングス株式会社
グループAI・DX本部 ビジネスITアーキテクト部
部長
2005年NTTコムウェア株式会社へ新卒入社し、人事給与システムの企画・導入を担当。ビジネスアナリストやプロジェクトマネージャーの役割を担った後に、2018年にパーソルホールディングス株式会社に入社。人事、財務系システムの企画・導入に従事し、2023年より現職。人事、財務、営業などのグループ共通業務のシステム企画・導入およびデータ利活用施策を推進中。
1

STRATEGY
【後編】未来の“はたらく”を変革する——パーソルホールディングス×パーソルクロステクノロジー 両本部長が語る、AI戦略と共創の最前線
2

PROJECT
わずか10カ月で開発・導入を実現。データドリブンなタレントマネジメント基盤を形にした舞台裏
3

PROJECT
課題の本質をとらえ、伴走型の支援を―コンサルティング×テクノロジーで拓く、地域共創の最前線
4

PROJECT
生成AIによって「女性のはたらき方」が変わり始めた―クラフター小島氏×パーソルテンプスタッフ朝比奈対談
5
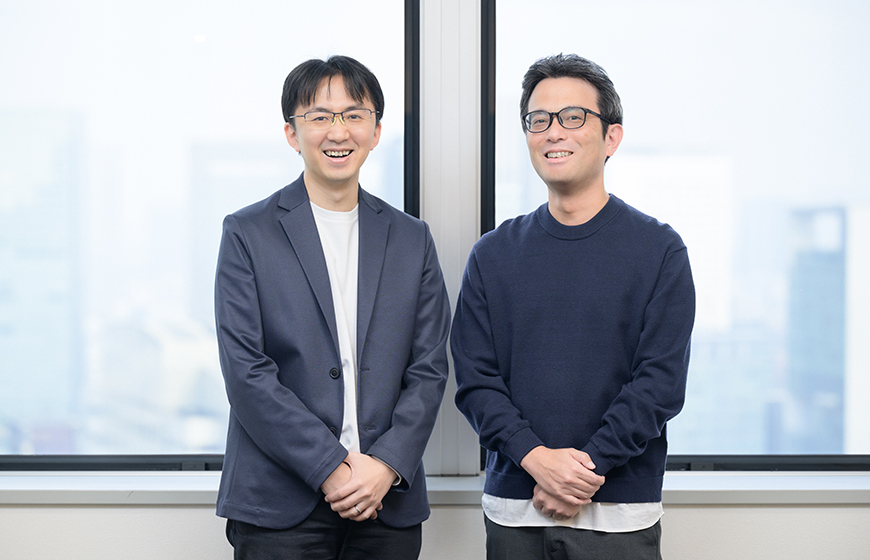
PROJECT
30を超える基幹システムを“無風”でクラウドに。パーソルテンプスタッフが挑むアプリリフト