PERSON
エンジニアからマネジメントの道へ―「とりあえずやってみる」から創り上げる、私らしいキャリア

2025年8月、書籍『企業競争力を高めるための生成AIの教科書: Generative AI × INNOVATION』が発売されました。
今回は、パーソルテンプスタッフの執行役員 CIOである朝比奈ゆり子が、同書の著者であり、女性起業家支援なども行っている株式会社クラフターの代表取締役・小島舞子氏との対談を実施。
生成AIが女性テクノロジー人材へもたらす変化をはじめ、ともにテクノロジーを軸にしたキャリアを歩んできた女性同士の対談をお届けします。

小島
生成AIの本格活用を検討する動きが顕著になる一方、実際に活用を進められている国内企業はまだ多くないことから、私の経験も踏まえて少しでも役に立てればという思いで執筆を開始しました。
例えば、企業のAI導入支援を行う中で「何から取り組みを始め、どう現場に定着させるべきか」「実務での活用がイメージできない」といった実務面の悩みがさまざま聞かれます。こうした点について、先行する企業の取り組みや気付きをまとめて読んでいただくことで、生成AI活用に悩む担当者の皆さんのお力になるのでは、と。


朝比奈
先日、パーソルグループの生成AI活用の社内コミュニティで、小島さんの書籍の情報をアナウンスしたら大きな反響がありました。私も何度も読み返していますが、豊富な実例がまとまっているのが良いですよね。

小島
ありがとうございます。

朝比奈
パーソルクロステクノロジーが主催するイベントに、ゲストスピーカーとして登壇いただいたことが最初のきっかけですよね。

小島
当時(2023年初頭)はまだ、生成AIに対して恐る恐る取り組んでいた企業が多かった印象です。そんな中、パーソルグループは大企業でさまざまな制約もあるはずの一方、内製化による先進的な取り組みを進めていたことにとても驚き、興味を持っていました。

小島
振り返ると「テクノロジー業界なら若いうちから活躍できそうだ」と思えたことが大きかったと思います。
私がテクノロジー業界に足を踏み入れた頃は、マーク・ザッカーバーグ氏が20代にして「Facebook」を成長させ、先行する競合他社を抜き去っていったタイミングでした。その姿を見て、自分も20代で世界中の顧客の行動変容を起こせるようなカルチャーを作って発信したいなと、テクノロジー領域での起業家の道を選んだんですよね。

朝比奈
私がはたらき始めたのは1990年代半ば、「ドットコムバブル」の頃です。インターネットが徐々に世の中へ浸透していき、たくさんのホームページが生まれ始めて……そうした新しいインターネットの世界に心が躍っていたので、この世界で手に職をつけることに魅力を感じました。
とはいえ、実は当初からこの領域を志していたわけではありません。もともとは「女性としていかにキャリアを築くか」を主眼に置いていました。当時、日本で女性が「はたらく」というと、大半が「制服を着てお茶を出し、コピーを取る」など補助的な仕事だったのですが、違和感があって。
そんな中、就職先として薦められた外資系ベンダーでは、女性社員が活躍してキャリアを築いていたんです。それが非常に魅力的に映りました。


朝比奈
私はもともとエンジニアだったのですが、多くのエンジニアと接する中で「技術面では絶対に敵わない」と思わされたことです。圧倒的な力の差を痛感したことで、現在に繋がるプロダクトマーケティングやテクノロジー活用・導入などでキャリアを歩み始めました。
あとは、前職の経験も大きいです。私の勤めてきた企業はM&Aされることが多く、前職でもM&Aされて、私はPMIを任されることになりました。ただ、プロジェクトメンバーの中には数カ月、あるいは数年後に解雇が決まっている人もいて、マネジメントに苦労したんです。
それまではグローバル企業らしい風土の下で「いかに仕事をシャープかつクリアに進めるか」に心血を注いできましたが、ここでの経験を経て、メンバーとともに泣いたり笑ったりしながらプロジェクトに取り組みたいと思うようになって。
最終的に、これまで歩んできた外資系から離れ、日系企業に飛び込んでみることにして、当時のインテリジェンス(現パーソルキャリア)への転職を選びました。

小島
クラフターを創業して社長になったことですかね。それまでは、どちらかと言えば「裏方」の仕事に徹して事業を効率的に進めることに注力するタイプで、引っ込み思案だったんです。しかし社長となると、自分から積極的に発信して、他の人を巻き込んでいかなければいけません。他社のトップも見ていて、この点は変わらなければいけないなと。
そこから、イベントに参加したら最初に必ず手を挙げて質問をするなど、小さなことから「発信」の練習をしました。せっかく時間を使って参加しているなら、その機会を無駄にせず、どうせなら一番目立って帰ろうと。失敗したこともありましたが、時間をかけて自信をつけていきました。


朝比奈
経験を重ねるごとに、ある意味で図々しくなって(笑)、「この新しい仕組みを使ったら今までにない体験ができるようになる」「こんなに良いものがあるなら、みんなやろうよ」と無邪気に言えるようになったと感じています。そして実際にどんどんと社内が変わっていくのを見るのは、とても楽しいです。

小島
無邪気さ、とても大事ですね。
私の楽しみで言えば「顧客視点で仕事をすること」です。そもそも、クラフターを起業したきっかけが、リクルート時代に痛感した「顧客の重要性」だったんです。いくつもサービスを企画してリリースする中、マーケティングやセールスがうまくいかないケースも少なくなくて「こんなに知名度も規模も立派な企業でも困っているんだ」と思い、関連するサービスを開発したいと思いました。
そうしたサービスを作ることはもちろん、社内のメンバーと一緒になって顧客に向き合いながら仕事できていることは、非常に大きなやりがいになっています。

小島
AIの進化によって、男女を問わず新たなキャリアを選びやすくなったと思います。特に、経験したことのない領域に挑戦するハードルが大きく下がりましたよね。

朝比奈
テクノロジー領域について、深い知識がなくても自分が思い描いたことを実現できるツールが数多く登場し、それも無料で使えるようになりました。自分の中で沸々としていた思いやアイデアを形にすることに、一歩踏み出しやすくなったはずです。

小島
人に相談できるほど準備の整っていない小さなアイデアも、AIになら「試しに聞いてみよう」と思えますし、壁打ちもできます。

朝比奈
あくまで私見ですが、これまで女性は男性よりも「ちゃんとしなさい」という圧にさらされやすかったのではないかと感じています。それが災いして、何をするにも100%に近い形に仕上げないと、と思ってしまう人が多かったのではないでしょうか。
それが、小島さんがおっしゃったように生成AIによって変わりつつあるなと。壁打ちしやすくなって、アイデアをブラッシュアップしやすくなりましたから。

小島
私なんか「海外に移住するとしたら、どこが良いと思う?」なんて質問も生成AIにしちゃってますよ(笑)。ものすごく気軽に質問できますよね。

朝比奈
「自分は素人だから……」という変な謙遜をする必要も、もうありません。複雑なロジックなども生成AIに聞けば、ある程度は教えてくれます。
あとは生成AIが「生まれたばかりのテクノロジー」だからこそ、あらゆる人が同じスタートラインに立っています。この点で、女性がイニシアチブを取りやすいのではないかとも感じています。パーソルグループの生成AIに関するコミュニティ内でも、積極的に情報発信しているメンバーには、女性が多いんですよ。


小島
皆さんに、自分の人的資本を厚くすることを考えてほしいと思っています。AI活用によって業務が効率化され、早く帰れるようになった分、自分の将来のために時間を使ってほしいなと。
例えば、これまで家庭のことなどに忙殺されて時間がなく、諦めていたキャリアに挑戦するのも良いですし、私みたいに「いつかできたらいいな」と思っている程度のプライベートな相談や、起業をAIに相談して考えてみるのも良いでしょう。「誰かのため」でなく「自分のため」に使う時間を、生成AIの活用によって増やしてほしいです。
私が「自分のため」を強調するのは、女性起業家支援に取り組む中で無償労働にまつわる悩みを多数耳にするからです。既婚女性の個人年収において、最も大きな割合を占めるのは「100万円未満」、500万円を超える人は20〜60代のいずれの年代でも数%にとどまります(※)。こうした、男性と大きく異なる状況が生まれる要因の1つは、子どもや家族のケア、親の介護といった無償労働に女性が当たらなければならないケースが多いことにあると考えられます。
※参照:男女共同参画局「特-55図 既婚者の個人年収(年齢階級別)」
そしてこれは個人の問題ではなく社会構造の問題ですから、生成AIが企業を変え、最終的に社会を変えていくことを期待しています。
私が理事を務める一般社団法人Women AI Initiative Japanでは、パーソルグループ様にもご賛同いただいている『女性のAIチャレンジ応援宣言』を企業の皆様とともに推進し、社会全体で女性のAIチャレンジを後押しするムーブメントの創出を目指しています。

朝比奈
あらゆる物事について「だいたいみんな同じくらいずつ」負担されるような、そしてその役割がジェンダーではなく個人個人の得意なものによって決まるような社会になれば良いですね。

小島
生成AIに触れる最初の段階としておすすめなのが「楽しくないこと」「好ましくないこと」を減らすのに使ってみることです。
報告書を書く、人事面談の前に個人レビューを書くなど、日々やらなければいけないけれど面倒な仕事があれば、生成AIに任せてみてください。きっと生成AI活用のハードルが下がるはずです。そして、短縮できた時間を自分の好きなことに充ててもらえたら嬉しく思います。

朝比奈
嫌なことを言わず、いつでも自分に寄り添って話を聞いてくれる生成AIは、皆さんにとっての「相棒」です。気兼ねせず幅広いことを相談してみてください。さらにその先で、活用の輪を個人から組織や事業へと広げて、社会を一緒に変えていきましょう!
取材・文・撮影=合同会社ヒトグラム
※所属組織および取材内容は2025年9月時点の情報です。
※略歴内の情報は2025年4月時点での内容です。

本記事に登場する、小島舞子氏著『企業競争力を高めるための生成AIの教科書: Generative AI × INNOVATION』は、こちらよりお求めいただけます。
1

STRATEGY
【後編】未来の“はたらく”を変革する——パーソルホールディングス×パーソルクロステクノロジー 両本部長が語る、AI戦略と共創の最前線
2

PROJECT
わずか10カ月で開発・導入を実現。データドリブンなタレントマネジメント基盤を形にした舞台裏
3

PROJECT
課題の本質をとらえ、伴走型の支援を―コンサルティング×テクノロジーで拓く、地域共創の最前線
4

PROJECT
生成AIによって「女性のはたらき方」が変わり始めた―クラフター小島氏×パーソルテンプスタッフ朝比奈対談
5
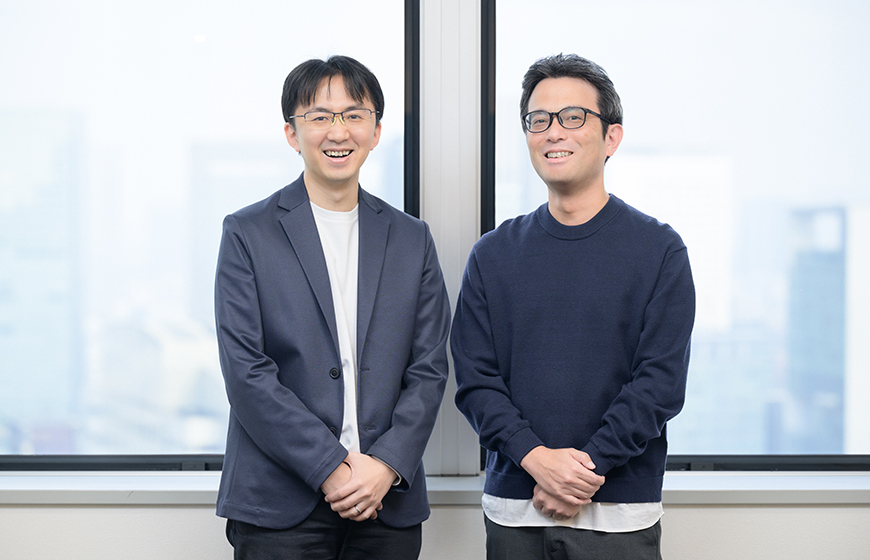
PROJECT
30を超える基幹システムを“無風”でクラウドに。パーソルテンプスタッフが挑むアプリリフト