PERSON
未経験からセキュリティ領域へ――専門性を磨きながらキャリアを広げ、自分らしく成長する

テクノロジードリブンの人材サービス企業を目指す、パーソルグループ。今回は、異業種からキャリアを築き、現在はITガバナンスを担う清水に、これまでの歩みと組織づくり、女性活躍の未来について聞きました。
大学ではドイツ語を専攻していましたが、番組制作に関わる仕事に憧れていたので、就職活動では大手制作会社を中心に挑戦していました。ただ、当時はまさに就職氷河期で、何十社と受けてもなかなか内定はもらえず、厳しい現実に直面していました。
そのような中で偶然にも卒業間近に見つけたのが、ドイツから輸入した電子部品向けのX線検査装置を販売するベンチャー企業の求人です。条件も良く、面接を受けに行くと「清水さんさえ良ければ来てね」と声をかけられ、思い切って入社を決めました。
社員10名ほどの小さな会社だったので、営業から製造・設置・保守・部品調達まで、経理以外のほぼすべての業務を経験しました。韓国や中国、シンガポールへの海外出張も一人で任され、振り返るとすごく貴重な経験だったと思います。
ただ、装置や重い荷物を運ぶことも多く、体力的に長く続けるのは難しいと感じるようになりました。そこで、未経験ながらIT業界への転職を考えるようになったんです。
2000年ごろは、Windows 98が普及し、インターネットが急速に広まり始めた時期でもあります。勤めていた会社でも、ビジネス用のホームページを立ち上げ、私はその保守も担当していました。
コードを編集するだけで文字やデザイン装飾が画面に反映されるのを見て、「こんなことができるんだ!」とすごく感動したのを覚えています。それが、「IT」という領域に強い興味を持ち始めたきっかけだったと思います。
当時はWebデザイナーとITエンジニア、どちらの道に進むかを迷っていたんです。ただ、まずは基礎的なスキルを身につけようと思い、仕事をしながらパソコンスクールに通い、デザインツールやプログラミング言語を学びました。
しかし、いざ26歳で転職活動を始めてみると、「未経験歓迎」と書かれていても、実は25歳までだったという“年齢の壁”に直面することが多く、苦戦していました。
なかなか思い通りに転職活動が進まない中で、「本当は25歳までだけど、清水さんは若く見えるからいいか」と言ってくれた企業があったんです(笑)。その面白さに惹かれ、2004年、客先常駐型のアプリケーションエンジニアとして、IT業界でのキャリアをスタートさせました。
その会社には3年間在籍し、未経験ということもあって簡単な保守業務からのスタートでしたが、徐々に要件定義・設計・開発・テスト・リリースまで、システム開発の一連の流れを経験することができました。
実は、プログラミングはまったく向いていなかったんです(笑)。同期の男性社員が「パズルを解くみたいで楽しい」と話す一方で、私は小さなバグに何度もつまずき、徐々に楽しさよりもストレスを感じるようになっていたんです。
さらに、当時は残業が月130時間を超えることも珍しくなく、そういう時代だったということもありますが、心身ともに疲弊していましたね。ただ、要件定義や設計といったお客さまと話しながら仕組みを考えていくプロセスは、すごく好きでした。
そのため、次はワークライフバランスを大切にしながら、自分の強みをより活かせる「サービス寄りの仕事」へシフトしようと決意しました。

転職活動中に「要望を聞きながら、システム導入を支援する講師のような仕事」の求人を見つけ、まさに「これだ!」と思い、アウトソーシングを手がける企業に転職しました。
ところが、いざ入社してみると、配属候補は「経理」「事務」「IT」の3部門で、求人票に書かれていた“講師”というポジションはなかったんです。今思えば辞退する選択肢もありましたが、気持ちを切り替え、再び客先常駐型のIT業務に身を置くことにしたんです。
大手ITコンサルティングファームの運用部門で、金融機関向けのID管理業務を担当しました。ちょうどJ-SOX法(内部統制報告制度)が施行され、IT運用にも統制やガバナンスが求められていたタイミングです。
その現場には、さまざまな専門家が在籍しており、実務を通じて内部統制の「社会的意義」や「実践的な知識」を深く学ぶことができました。そして、この時の経験が今のキャリアの土台になっていると思います。
最初はオペレーションメンバーでしたが、途中から業務を地方へ移管するプロジェクトにも参画することになりました。さらに、前任の退職により、心の準備もないままにプロジェクトリーダーを任されたんです。急な環境変化に加え、人員整理の判断も担う立場になり、健康診断では胃の再検査の判定が出るほど負担が大きくなっていました。
それでも10年間、懸命に向き合ってきましたが、待遇やキャリアの展望に変化が見られなかったため、常駐先との契約が終了したタイミングで、次のステップへ進むことを決意しました。
30代は「専門性を深めるべきか、幅を広げるべきか」ずっと悩んでいました。「常駐型派遣」という立場だったこともあり、明確な専門領域を築けている自信があまり持てなかったんです。
そんなときに信頼していた60代の職場の先輩にキャリアの悩みを打ち明けたところ、「専門性を突き詰めなさい」とはっきり言われたんです。40歳目前だった私には、その言葉が心に強く響き、これまで培ってきた内部統制の知識や経験を軸に、これからのキャリアを築いていこうと決めました。
そうですね。ただ、内部監査や、特にシステム監査系の求人数は非常に少なく、ほとんどが経験者限定の募集ばかりでしたが、幸運にも未経験で挑戦できる住宅関連サービス企業のシステム監査の求人に出会い、転職を叶えました。
内部監査業務では、リスクへの対応を経営の視点で考え、社外に説明する能力が求められます。背景を理解し、論点を整理し、自分の言葉でわかりやすく伝える――そうした力が、実務を通じて自然と養われていきました。
また、施策を進める際には、常に「事業戦略と整合性があるか」「組織として適切か」という視点を意識するようになりました。そうした視点で物事を捉える力は、現在のITガバナンスの業務にも活きています。

内部監査の仕事は、「これほど視野が広がった経験はない!」と言い切れるほど、得るものが大きい業務で、非常に良い経験が積めたと思っています。ただ一方で、社内には同じ役割を担う人がおらず、専門性が高すぎるがゆえに、今後のキャリアの道筋が描きにくいという個人的な悩みもできてきました。
これまで「現場でリスクを管理する立場」と「経営の視点でリスクを監督する立場」を経験してきました。そこで、次に目指したのは、その中間である「ルールを設計し、経営と現場をつなぐ立場」です。
その希少なポジションとして出会えたのが、パーソルホールディングスのITガバナンスの仕事でした。
国内外に何十社とあるグループ全体に、共通するルールを設計し、リスク管理の基盤を築いていく。そのスケールの大きさに強く惹かれ、2022年に入社しました。
これまでのキャリアを通して、「このタイミングで、こう言ってくれたら、こういう判断をしてくれたら、どれだけ救われただろう・・・」と、その時の上司に対して思った場面が何度もありました。だからこそ今は、自分が“伝える側”として、明確な方針を示し、チームに安心感と推進力を与えられる存在でありたいと思っています。
方向性を示し、意思決定を行い、意見の衝突があれば冷静に整理して前へ進めていく。そうした「道筋をつくる」ことこそが、室長という立場に求められる一番重要な役割だと考えています。
長く現場で手を動かしてきたからこそ、「こうしてほしかった」と感じた経験を活かし、“かゆいところに手が届くマネジメントのあり方“を、今度は自分が体現していきたいと思います。
ITベンダーに常駐していたときに出会った、クライアント企業の部長の影響がとても大きいですね。部長は、私からすると「お客さま」でしたが、10年近くご一緒するなかで、直属の上司のような関係性ができていて、とてもお世話になった方です。
業務には非常に厳しい一方で、常に私のキャリアや成長にも目を向けてくれる、そんな思いやりのある方でした。ちょっとしたひと言や態度に、人に寄り添う姿勢がにじみ出ていて、いまでも私の理想の上司像ですね(笑)。
ただ信頼して任せるだけではなく、相手の状況や気持ちに関心を寄せ、必要に応じて手を差し伸べる、メンバーとはそうした関わり方を大切にしていきたいですね。
IT業界は、1980年代に急速な成長を遂げた歴史を持ち、その過程で女性の活躍の場も少しずつ広がってきました。特にITエンジニアは「技術職」と括られることからも、性別にかかわらずスキルや成果を重視するフラットな文化のなかで、より活躍しやすいのだと思います。
私自身、これまで長くこの業界ではたらいてきましたが、「女性だから」と特別に意識させられる場面はありませんでした。IT業界は、女性が自分の力でキャリアを築いていきやすい環境だと思います。
パーソルグループでは現在、「女性管理職比率の向上」を重点テーマのひとつに掲げています。しかし、現場では「管理職の負担が大きい」という印象がまだまだ根強く、正直なかなか挑戦に踏み出せない方も少なくありません。
だからこそ、マネジメントを組織として支える体制を、今後さらに整えていくことが求められます。そのためには、「部下の育成」を、マネジメントの評価指標として明確に位置づけることが重要です。あわせて、管理職を支える上位職に対しても、「どのように支援・育成しているか」という観点からの評価やフィードバックを取り入れていく必要があります。
個々の能力や努力に依存するのではなく、マネジメントを“仕組みとして支える文化”を組織全体で育てていくこと。そうした支援と責任のバランスが整えば、女性に限らず誰もが安心してマネジメントに挑戦できる、しなやかで強い組織の実現につながると考えています。
これまでパーソルグループは、それぞれの会社の文化や自律性を尊重しながら成長してきました。その柔軟さはグループの大きな強みですが、現在は「さらなる成長に向けて、明確な方向性を打ち出していくフェーズ」に入っています。
そうした転換点において、私たちITガバナンス部門に求められているのは、まずパーソルホールディングスとしての役割や期待をきちんと言語化することです。そのうえで、グループ全体で、「何を、誰が、どこまで担保するのか」を共通言語で語れる状態をつくる必要があります。
小さな最適解ではなく、グループ全体がひとつのチームとして歩めるように。見えない課題を可視化し、連携できる基盤を整えることこそ、ITガバナンスとして果たすべき役割だと思っています。

取材=伊藤秋廣(エーアイプロダクション)/文=嶋田純一/撮影=白戸宏和(PalmTrees)
※所属組織および取材内容は2025年10月時点の情報です。
※略歴内の情報は2025年10月時点での内容です。

パーソルホールディングス株式会社
グループテクノロジー
ITガバナンス部 ITマネジメント室
室長
2000年に新卒でサービスエンジニアとしてキャリアを開始し、2004年にIT業界へ転身。ソフトウェア開発を経て、IT運用部門でJSOX監査対応など内部統制の体制構築を10年経験。内部監査部門でシステム監査を担当後、2022年にパーソルホールディングスに入社。ITガバナンスの構築・改善支援を経て、2025年10月より現職。
1

STRATEGY
【後編】未来の“はたらく”を変革する——パーソルホールディングス×パーソルクロステクノロジー 両本部長が語る、AI戦略と共創の最前線
2

PROJECT
わずか10カ月で開発・導入を実現。データドリブンなタレントマネジメント基盤を形にした舞台裏
3

PROJECT
課題の本質をとらえ、伴走型の支援を―コンサルティング×テクノロジーで拓く、地域共創の最前線
4

PROJECT
生成AIによって「女性のはたらき方」が変わり始めた―クラフター小島氏×パーソルテンプスタッフ朝比奈対談
5
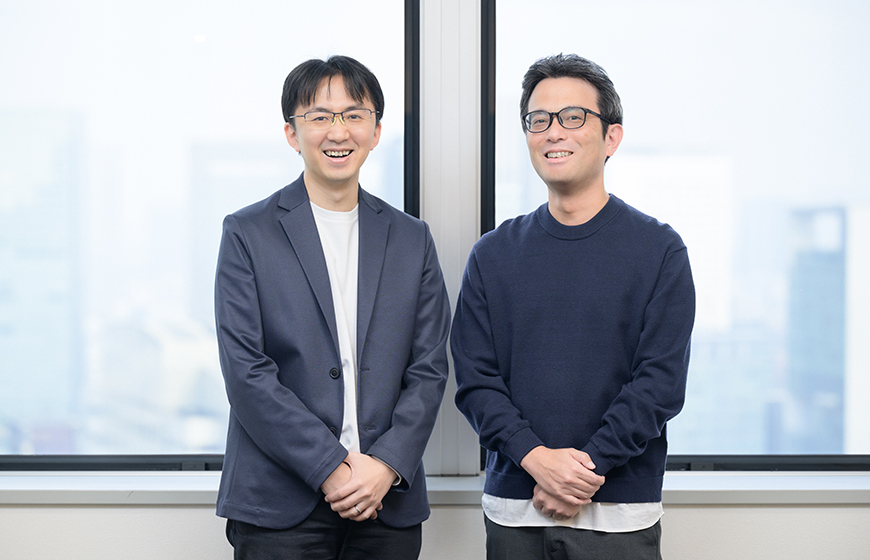
PROJECT
30を超える基幹システムを“無風”でクラウドに。パーソルテンプスタッフが挑むアプリリフト