PROJECT
国内38社6万人の業務基盤を支えるビジネスITアーキテクト部が挑む業務改革とは?

パーソルグループはいま、「テクノロジードリブンの人材サービス企業」への進化の半ばにあります。その中核となる組織のひとつが2023年11月に新設された「データ利活用推進室」です。
組織に課せられたミッションと最新の取り組み、さらに今後の展望について、同室の取り組みを率いる久野に聞きました。
データ利活用推進室は、パーソルグループ各社のデータ活用を推進する専門組織として2023年11月に設立されました。「BITA」とは「Business IT Architect」の略で、グループ各社の業務用アプリケーションの導入・改善を通じて、業務効率化を支援することをミッションとする組織です。
なかでもデータ利活用推進室は、データドリブンな環境づくりを通じてグループ全体のビジネス価値向上に貢献するために、人事、セールス&マーケティング、財務領域など、各業務領域を担当するBITA室と連携しながら、データドリブンな体制構築に挑んでいます。
そうですね。もちろんこれまでも各BITA室主導でデータ利活用を進めていましたが、その取り組み内容や進捗には濃淡がありました。また、それぞれがそれぞれの仕様でデータ基盤の整備を進めてしまうと、データの重複をはじめとするさまざまな問題が生じかねません。そこで、領域横断で全社におけるデータ利活用の環境づくりを主導する組織として、データ利活用推進室が生まれたわけです。
2025年度はさらにカバーする領域を広げ、新たな施策の立案や新規プロジェクトの立ち上げを通じて、データ利活用に弾みをつけたいと考えています。
われわれが目指す「データ利活用」は、次の3つの段階を経て達成すべきものだと捉えています。最初のステップは「必要なデータがあるべき場所に集められている」状態、その次が「収集したデータが必要なときにいつでも見られる」状態、そして最終的なゴールは「データをビジネスの発展や成長に活かしている」状態です。データ利活用推進室は、グループ各社が3ステップ目のゴールを見据えながらデータの利活用のレベルを上げられるよう後押しする組織だと自負しています。
先進的な取り組みを進めているパーソルキャリアを筆頭に、データの収集と可視化の面ではある程度形になっている一方で、データをもとにしたビジネスの見直しや新規立ち上げについては、今後の課題です。
仮に理想的な状況を100とし、パーソルグループのビジネスと保有するデータのポテンシャルを踏まえると、個人的には50に手が届くかどうかという活用レベルではないかと思います。とくに新たなビジネスの創造という観点でのデータ利活用については、まだまだ伸び代があるという認識です。

みなさん概ねデータの利活用の必要性を理解していただいている印象です。少なくとも他社事例などでよく耳にする、データ利活用に否定的な「抵抗勢力」がいないとは感じています。もちろん現時点での活用レベルはさまざまです。しかしデータの重要性や可能性に対する理解は進んでいるので、誰でもデータを自由に使いこなせる環境が整い、かつ身近な成功事例が増えれば、自ずと業務改善やビジネスの成長に大きなインパクトを残す施策が増えるだろうと見ています。
その上で施策の精度を高めるには、失敗を含めた経験の数が重要です。データ利活用に近道はありません。まずは、データから蓋然性のある仮説を立て、検証と改善のサイクルを高速に回転させる仕組みや環境を整えなければならないと思っています。
データ利活用においては、グループのなかでもパーソルキャリアが頭ひとつ抜きん出ているので、彼らが積み上げた経験や実績を踏まえながら、今後はIT部門以外にもデータの利活用の輪を広げていくつもりです。
この1年間は、主として人事領域やセールス&マーケティング領域でのデータ利活用環境の整備に取り組んでいました。
膨大なデータのなかから本当に必要なデータに辿りつくには、一定の知識と経験が必要です。かといって、毎回、データを管理している部門や担当者を探し、助言を求めなければならない状態のままでは、なかなか活用レベルは上がりません。そこで昨年秋から、セールス&マーケティング領域の一部データを手始めに、属性などのメタデータを付与するデータカタログプロジェクトを開始しました。いまはまだPoC段階ですがもし結果がよければデータアナリストやデータサイエンティストに利用してもらった後、タイミングを見計らって誰でも利用できる形で全社展開できればと思っています。
従来のデータ利活用のあり方を見直しプロセスを再構築するプロジェクトにも携わっています。一例を挙げますと、過去に取り組んだ人事領域のデータ利活用プロジェクトが、効率的とはいえない状況が温存されていたんです。簡単にいうとデータウェアハウスに集積した人事データから必要な情報を抽出し、BIツールを使って可視化していたのですが、データの収集や加工を手動で行っているプロセスが多く、かなりの工数と時間が費やされていました。
そこで、データの収集・加工を行う基盤を刷新し手動作業の多くを自動化したところ、一部のプロセスにおいては作業時間を1/2以下に短縮できました。手動作業を無くすことで、人的なミスの削減にもつながりました。また、無駄なツールやサーバを除去し、全てをサーバレス技術を使って構築したため、インフラの保守に関わる工数も削減することができました。
このように、われわれは新たなデータ利活用環境を整えるだけでなく、すでにある仕組みを見直し、活用レベルを高める取り組みにも力を入れています。
先ほど話したデータマネジメントを実現するにしても、教科書に載るようなベストプラクティスが確立されているわけではありませんし、他社の成功事例がそのまま当てはまるわけでもありません。パーソルグループに合った手法を見つけるところからスタートするので、その点が難しいところですね。
グループ全体の意識とリテラシーを高め、パーソルグループ全体に普及した後も試行錯誤は続くでしょうが、各社の事業を担う人たちとともに課題解決にあたるDX推進部の協力もあるので、必ずできると楽観しています。ほかの仕事と同じようにわれわれの仕事も難しさと面白さは表裏一体。私自身、難しい課題と向き合うなかで思いついたアイデアをさまざまな人にぶつけ、試しながら答えを探る過程を楽しんでいます。

先ほどご紹介したメタデータを付与してデータカタログを整備する取り組みが好例ですが、データを自在に扱える環境を整えることは、いずれパーソルグループにおける生成AI活用に弾みをつけることになるのではと見ています。なぜなら、データの持つ価値や意味を含んだメタデータを含む膨大なデータを生成AIに読み込ませれば、人間には到底およばないスピードで高精度なアウトプットが出せるかもしれないからです。
もしそれが実現できれば事業を預かる人たちにとっても強力なパートナーになるのは間違いありません。これはあくまでも個人的な願望を含んだ見立てではありますが、いずれにしても今後も引き続き、データを通じてパーソルグループの未来を切り拓く挑戦をし続けるつもりです。
もちろんデータマネジメントに関する知識や経験が必要なのは間違いありませんが、それ以上に大切な資質があります。それは目指す理想に向けてチャレンジし続ける熱意です。不確実性が高く、手探りではじめなければならなくても、ゴールから逆算していま取り組むべきことに集中できる方とご一緒したいですね。データ利活用の推進はひとりの力ではなしえません。定型的な仕事を黙々とこなすより、周囲を巻き込みながらトライ&エラーを繰り返せる人が向いていると思います。
そう思います。すでに誰かが持っている「答え」をそのまま実現する仕事ではありませんからね。われわれのミッションは、現場の人たちになり代わってデータ利活用に取り組むわけではなく、現場自らがデータを使って課題を解決したり、ビジネスを興したりできる状態を実現することにあるからです。ですから、お客さまの願いを聞き届ける「御用聞き」ではなく、同じ課題を共有する「伴走者」であるべきだと思っています。
われわれはいま、パーソルグループのデータ利活用を一段も二段も高いレベルに押し上げるという大きな目標に挑んでいます。この先、しんどいこともあるかもしれませんが「だからこそ面白い」と感じる前向きな方とパーソルグループのデータ利活用を盛り上げていけたら嬉しいですね!
取材・文=武田敏則(グレタケ)
※所属組織および取材内容は2025年5月時点の情報です。
※略歴内の情報は2025年10月時点での内容です。

パーソルホールディングス株式会社
グループAI・DX本部 ビジネスITアーキテクト部
データ利活用推進室
シニアコンサルタント
2004年、株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)に入社。人材紹介や求人広告の営業を経て、2009年からは営業企画にて法人顧客向けのマーケティングや新人研修などを担当。2012年に社内システム部門に異動後、PMとしてさまざまな業務システムのリプレイスを伴うBPRプロジェクトを推進。2020年からはパーソルホールディングスでデータ統合基盤の構築や活用促進に携わる。2023年11月から現職。
1

STRATEGY
【後編】未来の“はたらく”を変革する——パーソルホールディングス×パーソルクロステクノロジー 両本部長が語る、AI戦略と共創の最前線
2

PROJECT
わずか10カ月で開発・導入を実現。データドリブンなタレントマネジメント基盤を形にした舞台裏
3

PROJECT
課題の本質をとらえ、伴走型の支援を―コンサルティング×テクノロジーで拓く、地域共創の最前線
4

PROJECT
生成AIによって「女性のはたらき方」が変わり始めた―クラフター小島氏×パーソルテンプスタッフ朝比奈対談
5
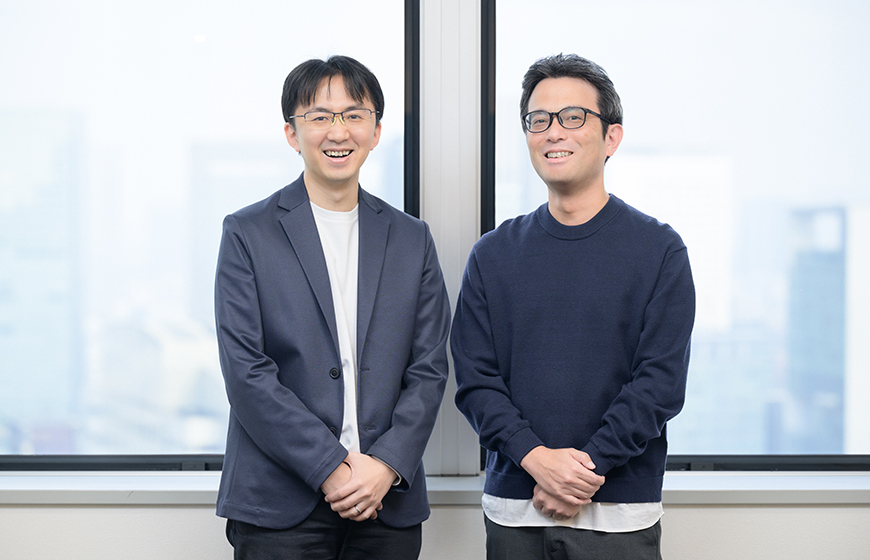
PROJECT
30を超える基幹システムを“無風”でクラウドに。パーソルテンプスタッフが挑むアプリリフト