STRATEGY
【前編】生成AIで変革を加速せよ——パーソル各社の事業をアップデートするグループAI・DX本部の挑戦

パーソルホールディングス株式会社
グループAI・DX本部
グループAI推進部
AIガバナンス室
室長
2003年、自動車開発会社に入社。その後、金融機関勤務を経て、2011年に日本年金機構に入構。お客さま対応や滞納処分業務に従事した後、年金システムの刷新プロジェクトに参画。2023年にパーソルホールディングスに入社し、テクノロジードリブンな人材企業を目指してグループ各社のDXを推進する。
パーソルホールディングス株式会社
グループGRC本部
法務部 戦略法務室
エキスパート
2007年、DeNA入社。営業や内部統制業務を経験。その後、複数のIT系ベンチャー企業において、法務・情報セキュリティ・業務改善(BPR)に関わる複数のプロジェクトをリードし、10名程度のチームマジメントも経験。法務や情報セキュリティの観点から、幅広くリスク対応と効率化を支援。2023年よりパーソルホールディングスに入社。戦略法務室でプライバシーガバナンスや人権に取り組むプロジェクトに参画。生成AIの利活用推進のためにグループ向けのガイドラインを策定。
2025年7月、パーソルホールディングスは「パーソルグループAI基本方針(以下、AI基本方針)」を公開しました。急速に進化するAIとその活用法の是非が問われるなか、方針の策定を主導した担当者はどのような思いで課題と向き合ったのでしょうか。AI基本方針の舞台裏とこれからの展望について話を聞きました。

岩崎
私は、2023年にパーソルキャリアのITポリシーを再整備するプロジェクトに携わった経験を買われて、今回このプロジェクトに参画することになりました。私が主に担当したのは、AI基本方針の素案づくりやグループ各社との調整、有識者を交えた説明会の開催などです。4月に新設されたグループAI推進部AIガバナンス室では、AIの利活用を進める立場からガバナンスの整備に携わっています。
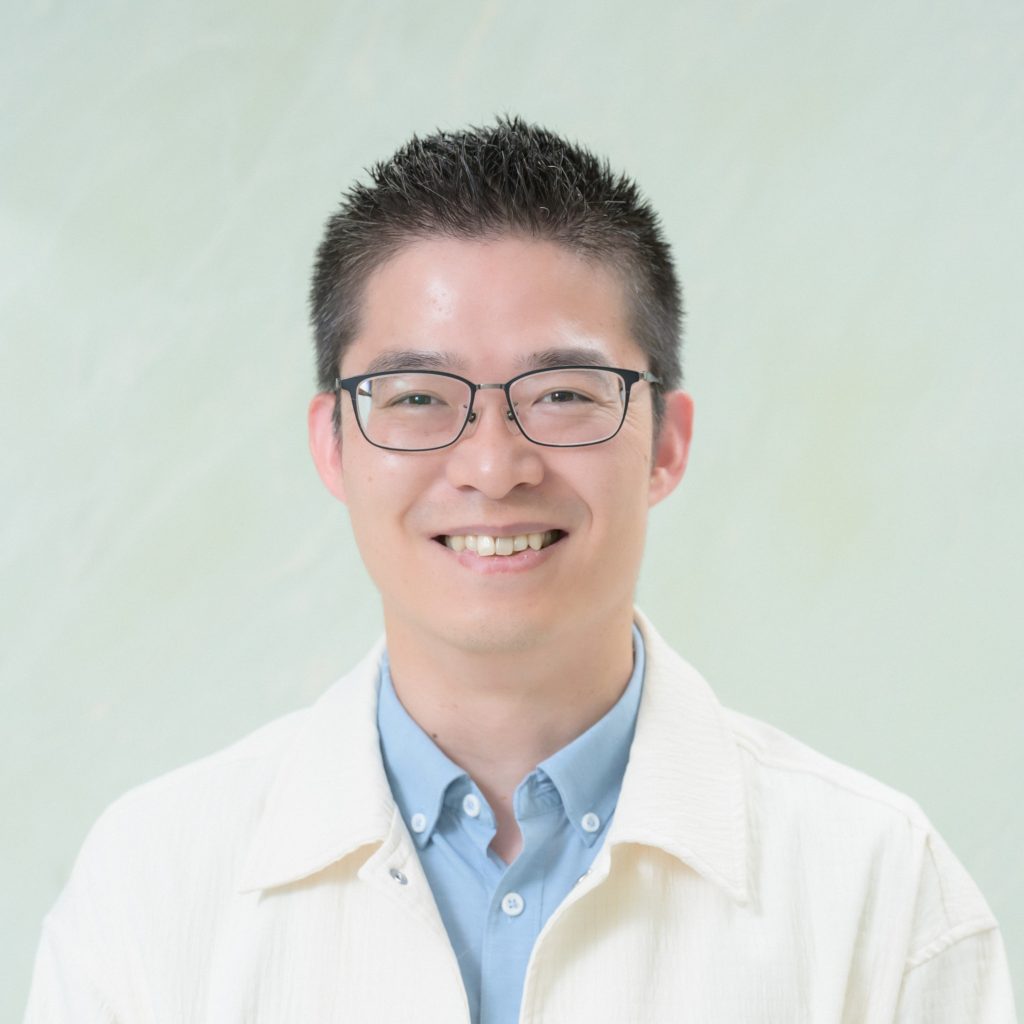
安原
岩崎さんがAIの利活用を推進する立場だとすると、私はグループのガバナンスやリスクマネジメントの立場からプロジェクトに携わりました。こうお話すると、AIの利活用を抑制するためのブレーキ役を務めたと思われるかもしれませんが、実際は少し違います。われわれに託されたのは、あくまでもAIの安全かつ適切な利活用を推進するための方針づくりだからです。
今回のプロジェクトでは、素案づくりや関係各位との調整を岩崎さんに担っていただいていたので、私は主に素案に寄せられたフィードバックを条文に取り入れるにあたって、条文に用いる言葉や表現について一緒に検討したり、ガバナンス・リスク・コンプライアンスの観点からのコメントを伝えたりする役割を務めました。
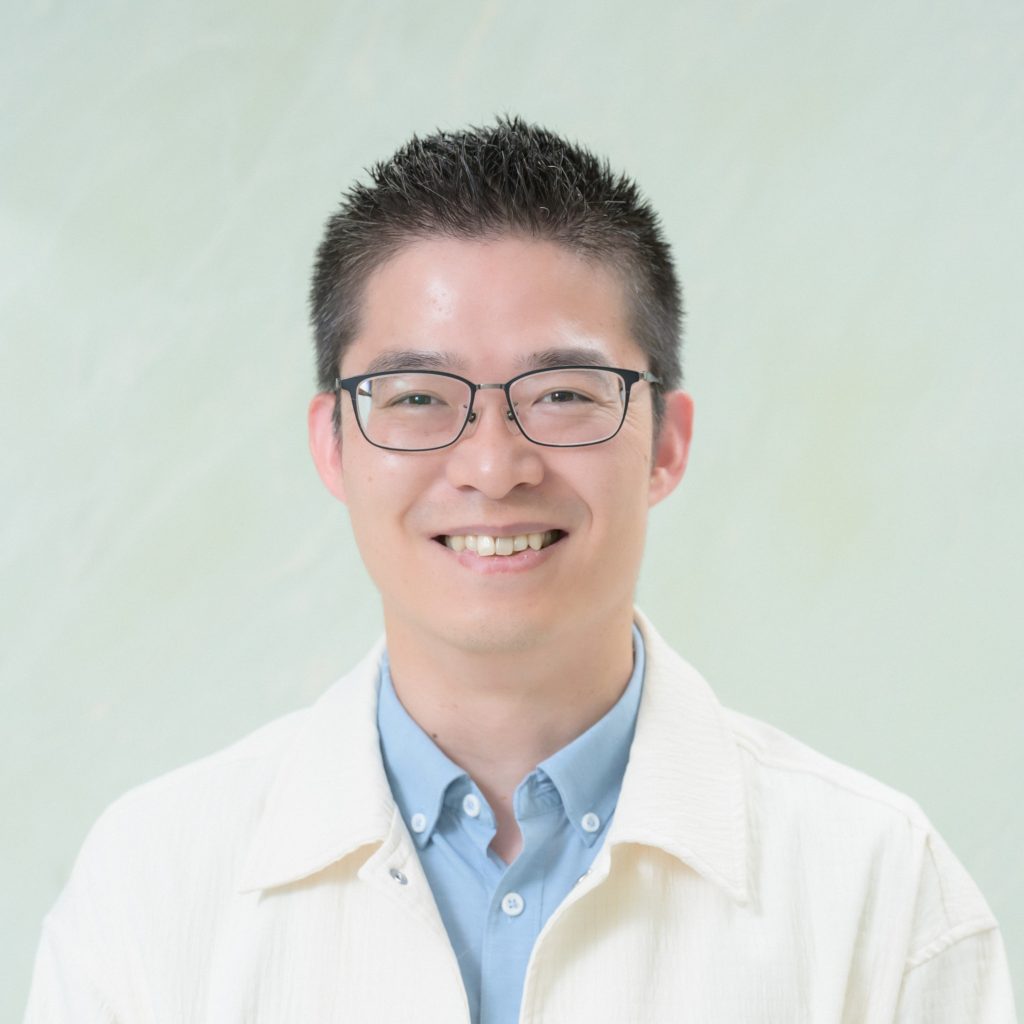
安原
これまでもパーソルでは、パーソナルデータ指針やプライバシーポリシーに則り、データの適切な取り扱いと利活用に取り組んでいました。ですから既存の枠組みのなかで、AIの利活用に取り組むこともできたのですが、AIの進歩は目覚ましく、その存在感は増すばかりです。当初、AIだけを切り出して基本方針を定めるべきかどうか議論がありましたが、当グループのAIに対する考え方を問われた場合、ご説明すべき要点や順序はパーソナルデータとは異なってきます。そこで、グループ全体の取り組みとして、AIに対する考え方を正面から示すべきだという結論に達し、AI基本方針を策定する方向に舵を切りました。

岩崎
確かにAIの利活用に関して、改めてポリシーを設ける必要があるのかという議論はありました。しかし、AIは業務効率化のための手段から、経営戦略の実現になくてはならない要素になる可能性が高く、ガバナンス担当者など、一部の社員だけがAIの適切な利活用について理解していれば済むというわけにはいかなくなることは明白でした。そのため、「AIをどのような考えに基づいて利活用しようとしているか」をいち早くパーソルグループとして社会に示すことが、われわれに対する信頼を高める結果につながるのではないかと考えたことも、AI基本方針の策定に踏み切った大きな理由のひとつです。


岩崎
グループ各社のプライバシー保護責任者やガバナンスの関係者に、AI基本方針を定める背景や目的を説明するための資料づくりにはじまり、条文の素案づくりと関係者へのプレゼン、さらに、各社から寄せられたフィードバックをもとに手を入れた条文を再度確認、までの一連の作業を繰り返し、徐々に内容をブラッシュアップしていきました。このプロジェクトがはじまったのは2024年8月で、そこから半年以上を費やして条文を固め、2025年7月1日に公開に漕ぎ着けました。

岩崎
たとえば、以前私が携わったプロジェクトであれば「COBIT(Control Objectives for Information and related Technology)」や「PMBOK(Project Management Body of Knowledge)」など、参考になるフレームワークがすでに確立されており、企業での導入事例も豊富です。一方でAIは、全世界的に見てもまだ手探り状態が続いています。そのため、まずは欧州連合が制定した「EUAIACT」や、米国国立標準技術研究所の「AIRiskManagementFramework」、国内だと内閣府による「人間中心のAI社会原則」や、経産省の「AI事業者ガイドライン」など、複数のリソースを参考にし、自社にあった形をつくらなければならない難しさがありました。
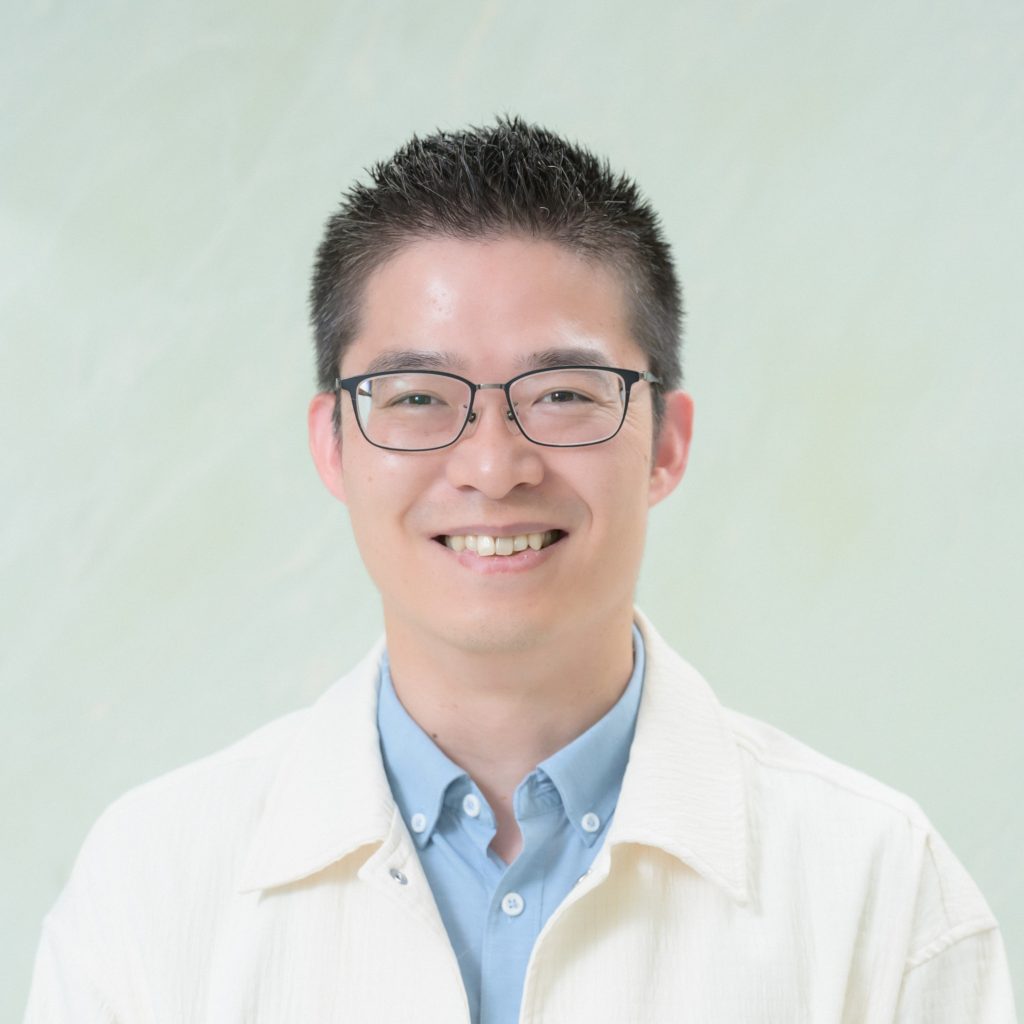
安原
当グループの基本方針は最終的に 8つのキーワードを立てることとなりましたが、各キーワードの内容を説明する文章の作成にも難しさがありました。キーワード自体は多くの人が聞いたことのある言葉ですが、それぞれの意味を深堀し、きちんとした説明文を作るとなるとかなりボリュームがある内容となってしまいます。そのため、基本方針として掲げるにあたり、各キーワードの説明文について、当グループにとって重要な要素をコンパクトに選び出す必要がありました。その選定にあたっては、関係者に AI そのものや AI ガバナンスに関する理解を深めてもらうとともに、各事業に関する知見を集結させて進めることが求められました。

岩崎
さらにパーソルグループは、国内だけで38社、海外法人は111社もの企業からなっています。事業内容も、人材派遣や転職サービスのような人材業のど真ん中のビジネスだけでなく、コンサルティングやSaaSなど、法人向けのソリューションサービスもたくさんあります。さらに事業内容だけでなく、組織体制やAI活用のスタンス、活用レベルも異なるなか、各社の意思を条文に込めなければなりません。議論の深まりとともに、思いも寄らなかった視点や難しさに直面することが、たびたびありました。

岩崎
文章の細部に至るまで検討が必要でした。例えばですが、AIを活用する際、もっともらしい誤情報を生み出してしまう「ハルシネーション」を絶対に起こさないと断言することはできませんし、だからといって「AIが出したアウトプットは必ず人間がチェックします」というのも現実的ではありません。そこで、そもそも我々がどのような責任を果たしていくのか、ということを伝えるべきだと考え、「人がすべきこと・AIに任せていいことを我々が責任をもって判断する」という表現にすることで、分かりやすくなるように対処しました。ほかにも、われわれのお客さまが多岐にわたることを考慮し、ステークホルダーの権利を脅かすことのないAIの設計・開発に努めることも明記するなど、推敲を重ねるなかで、細かな部分も含めると変更点は数え切れないほどです。社内の関係者に加え、法律や倫理に詳しい弁護士や大学の先生にも意見をいただき練り上げたのが、いまのAI基本方針なんです。
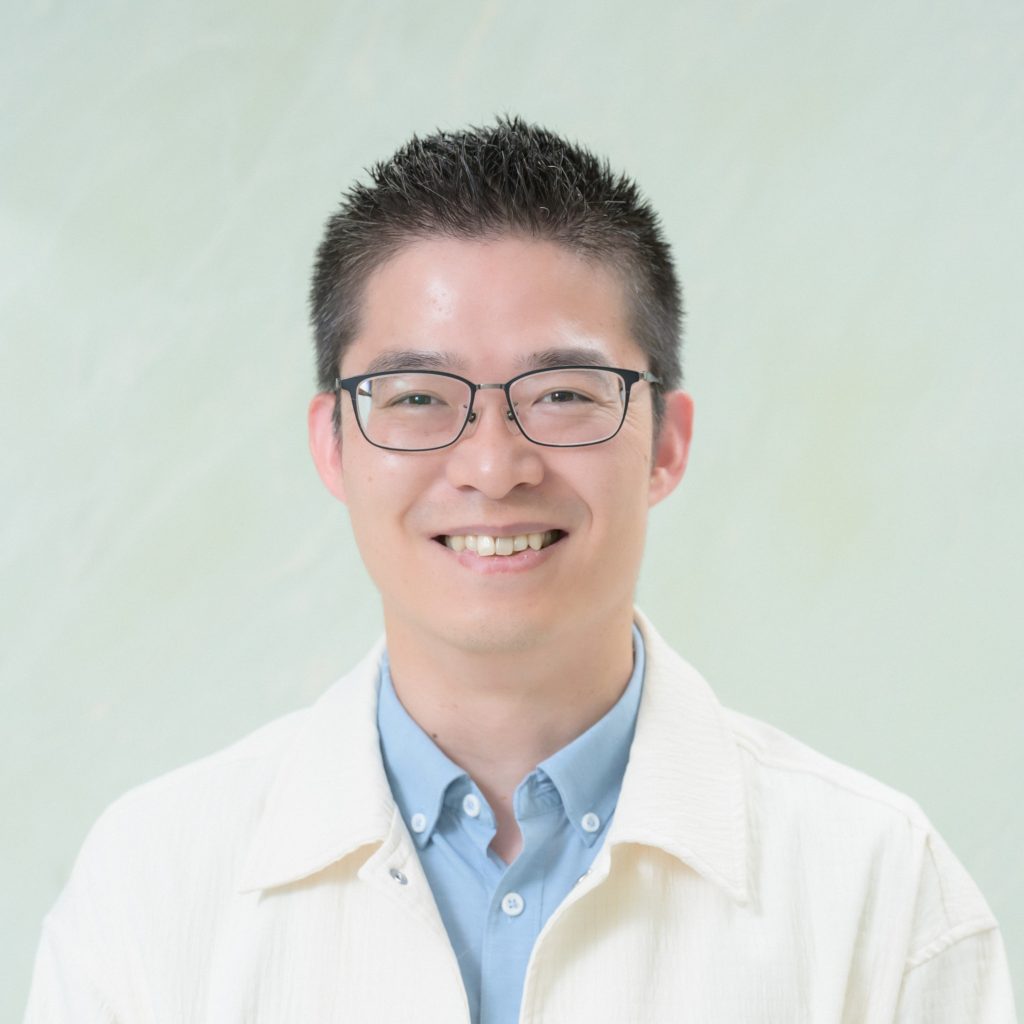
安原
AIの進化ですぐに陳腐化してしまっては、基本方針とうたうにはこころもとないですし、人によって言葉から伝わるニュアンスや受け取り方が変わってしまうのも適切ではありません。普段、どのようなビジネスに携わっていたとしても、条文の表現に違和感を覚えることがないよう、岩崎さんと一つひとつの言葉を吟味したので、その点は少し大変でしたね。

岩崎
条文の素案を関係各位に見てもらうと、たいていは総論OKなのですが、文言レベルのディテールになると、さまざまな意見が飛び交うことになります。国内のグループ会社に加え、海外のグループ会社とのやり取りもあったので、こちらも一筋縄ではいきませんでした。海外グループを含む関係各位と意見を交わしては条文を改稿する、ということを繰り返しましたので、おそらく改稿作業は6回以上におよんだと思います。一方で、パーソルならではの色を出したいという声も多かったので、新たに前文を設けるなど、さまざまな工夫を凝らしました。この前文には、グループビジョンである「はたらいて、笑おう。」と、パーソルグループが目指す企業像である「“はたらくWell-being”創造カンパニー」という言葉とともに、個々の価値の尊重や多様な人々が活躍できる社会の実現といったパーソルとしての想い、AIに関する考え方、お客さまに対する約束を込めました。
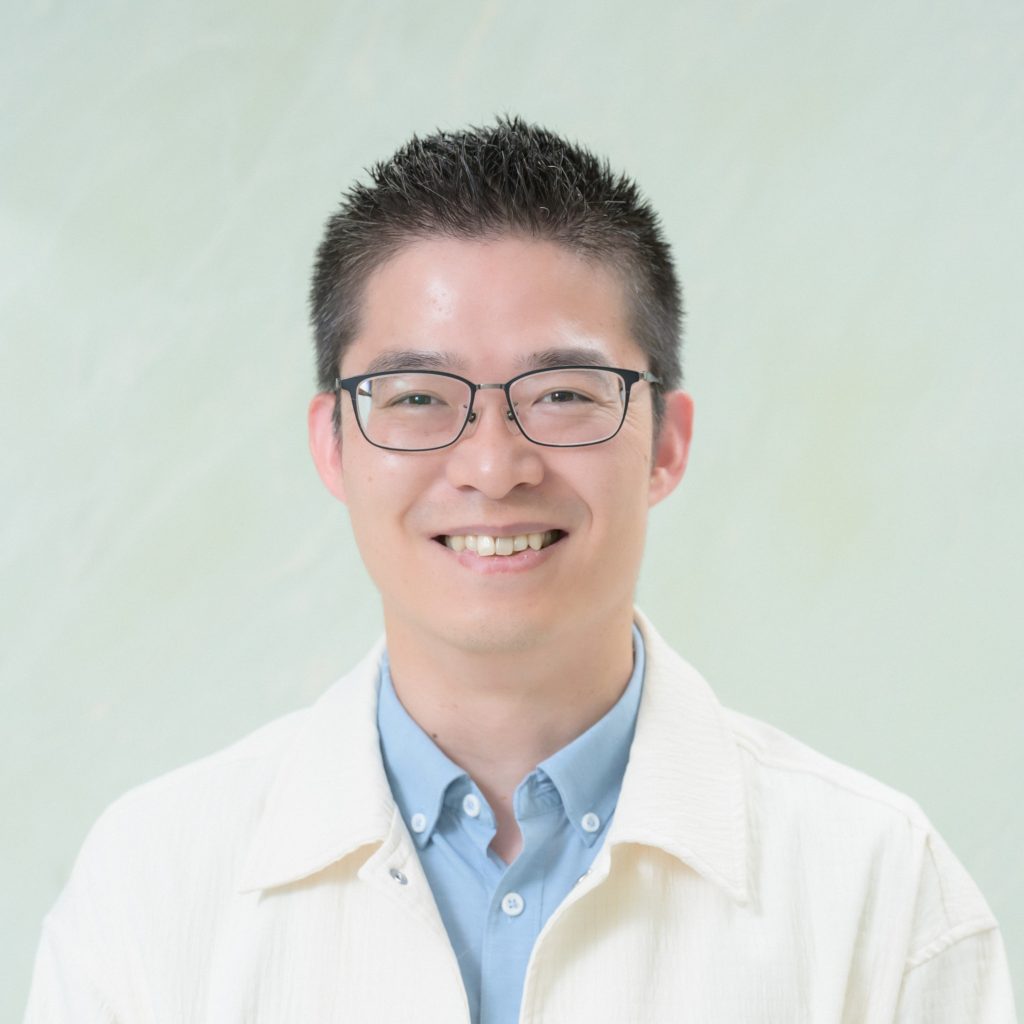
安原
岩崎さんが関係者の意見をうまく取りまとめてくださっていたので、私は全体の整合性を整えることを意識していました。私たちの立場や役割の違いでふたりの認識が大きくズレることは、ほとんどなかったように思います。

岩崎
そうでしたね。関係者に改稿案を見せる前に、安原さんに「これで意図は伝わると思いますか?」などと、よく相談を持ちかけていました。私は安原さんに全幅の信頼を置いていましたから、「大丈夫」と、お墨付きがもらえると自信を持って説明できました。そういう意味でも、安原さんはとても心強い存在でしたね。


岩崎
今後は、AI基本方針に基づいて、リスク審査やプライバシー保護のあり方を随時見直していくことになります。既存事業に限らず、AIを活用したR&Dや新規事業も増えるはずなので、むしろこれからが本番といえそうです。
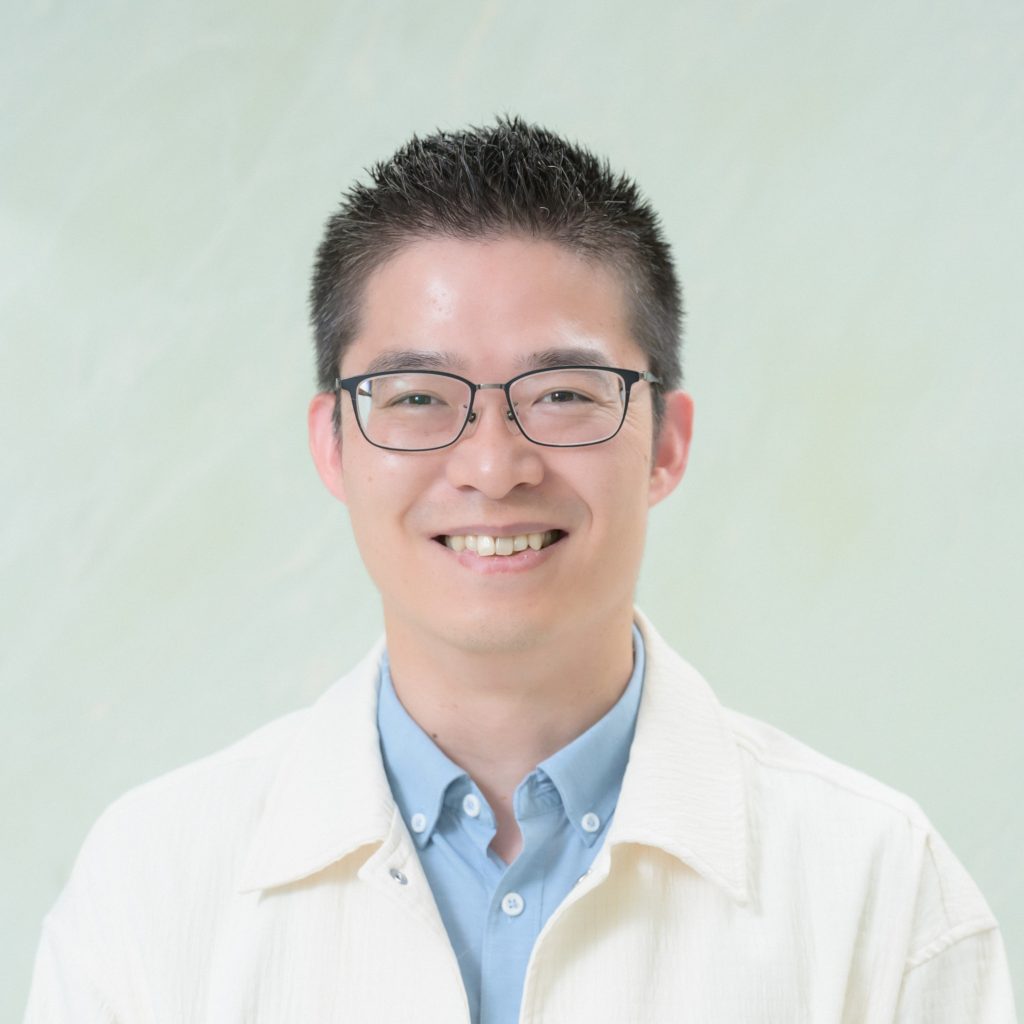
安原
AI基本方針ができたことで、施策や取り組み内容がレベルアップしていくことが大切なので、岩崎さんのいうように、今後はその実現のための支援に回る機会が増えそうです。これからはAI基本方針の実効的運用に貢献できればと思っています。

岩崎
AI基本方針はいうなれば、パーソルグループのAI利活用における「憲法」のようなもの。経年変化に強い内容になっているとはいえ、いずれAI事業者ガイドラインの改定もあるでしょうし、将来的にAIの利活用に大きな影響を与える状況に直面するかもしれません。いつそんな状況になっても対応できるよう、AI利活用の推進をしながらも、変化への備えをしておきたいと思っています。

岩崎
AIはこれからの社会を支える重要な基盤になるはずです。そのAIの利活用の基本方針づくりに携われたことは名誉なことですし、さまざまな困難を乗り越えて内外に示すことができたことで、仕事への自信にもつながりました。
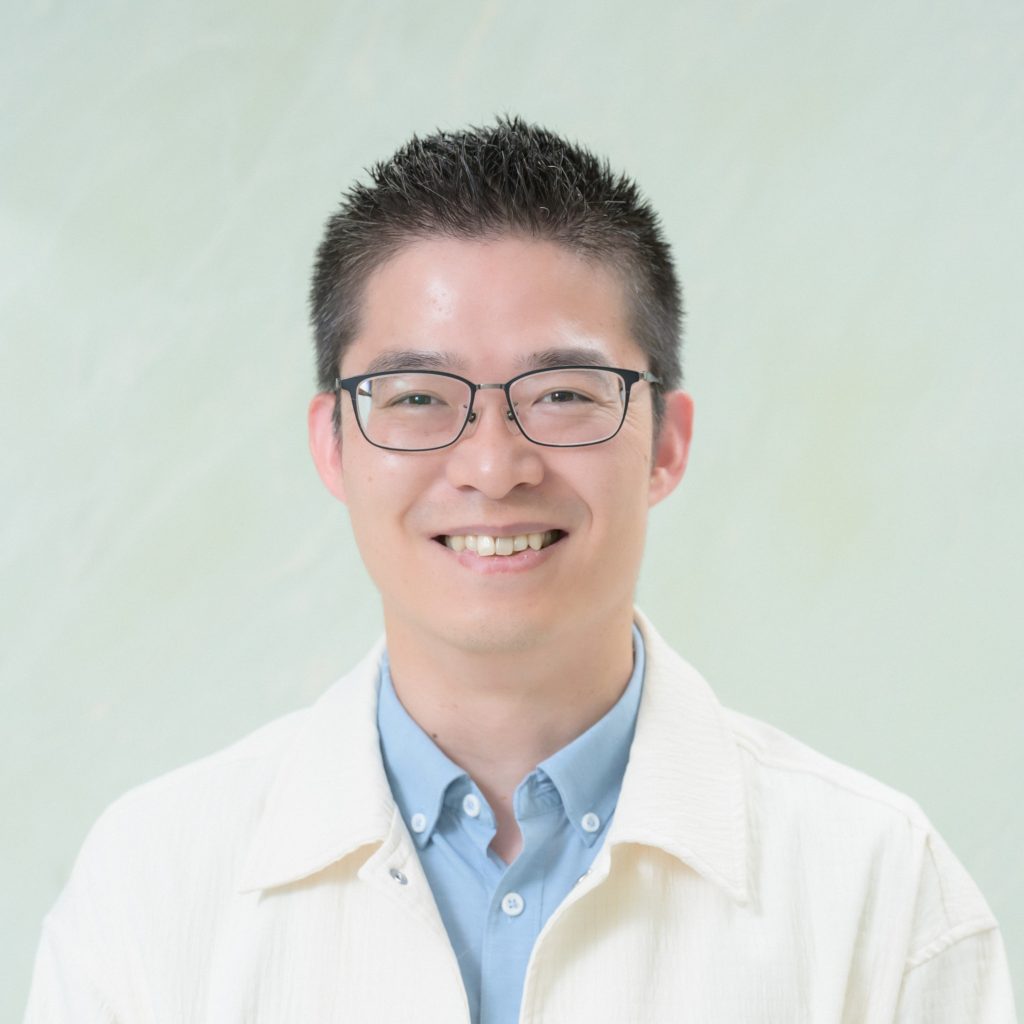
安原
とてもエネルギーが必要な取り組みではありましたが、AI活用のスピードを緩めず、正しい意思決定を下すための土台づくりに参加できてよかったと思います。このプロジェクトを通じて、パーソルグループ各社のビジネスへの解像度が高まり、AIへの理解も深まりました。グループ全体に影響をおよぼす方針づくりに携われる機会は滅多にあることではありません。いい経験ができたと思います。

岩崎
業務効率化や省力化だけでなく、AIの活用で人間の創造性が高まったり、新しい価値を創出できたりするような使い方が増えたら嬉しいですね。はたらくすべての人が幸せになるような使い方が広がり、人々の生活にポジティブな変化をもたらしてくれたらと願っています。
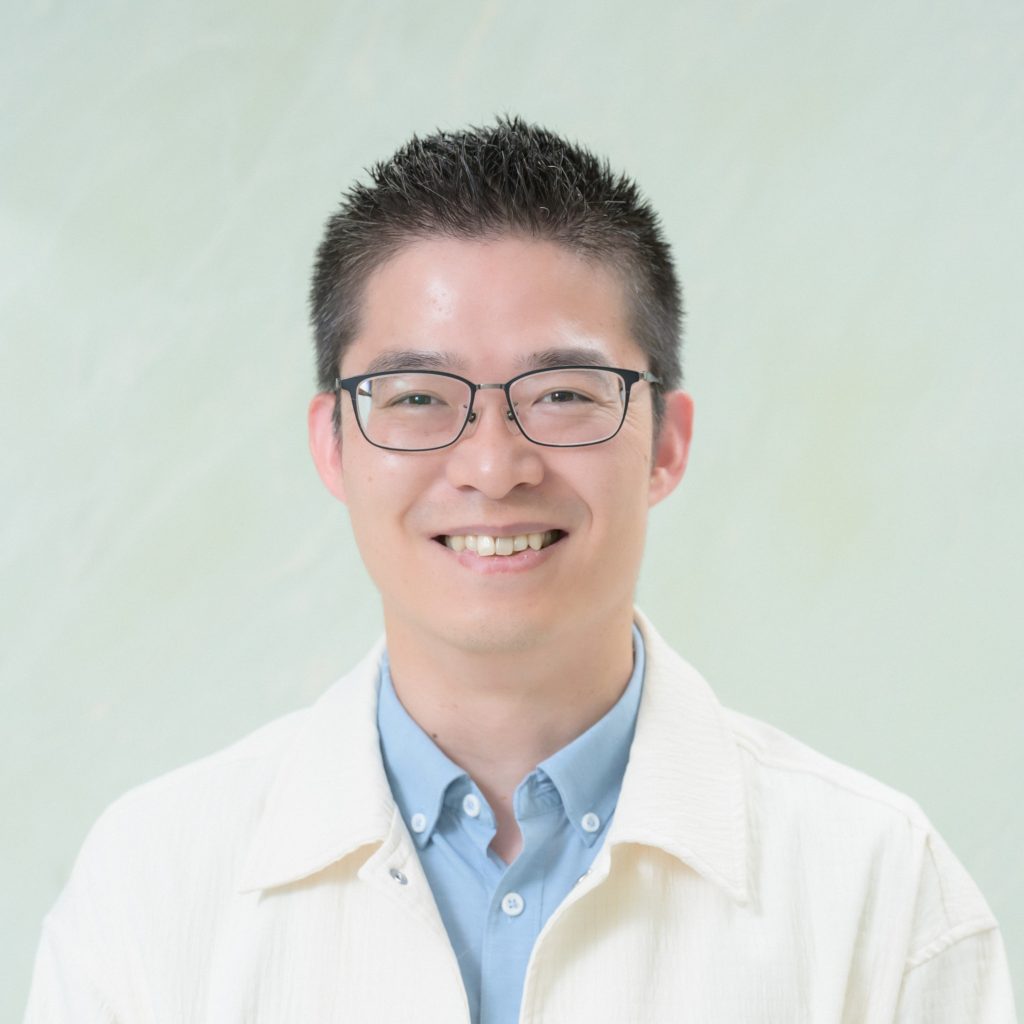
安原
同感です。私も日頃からリサーチや契約書の文言調整の補助にAIを活用していますが、業務効率化に留まらない活用をしたいですし、よりよい使い方が広がった結果、幸せになる人が増えれば、基本方針の策定に携わった甲斐があります。パーソルのビジネスはもちろん、社会にもいい影響を与えられたら嬉しいですね。
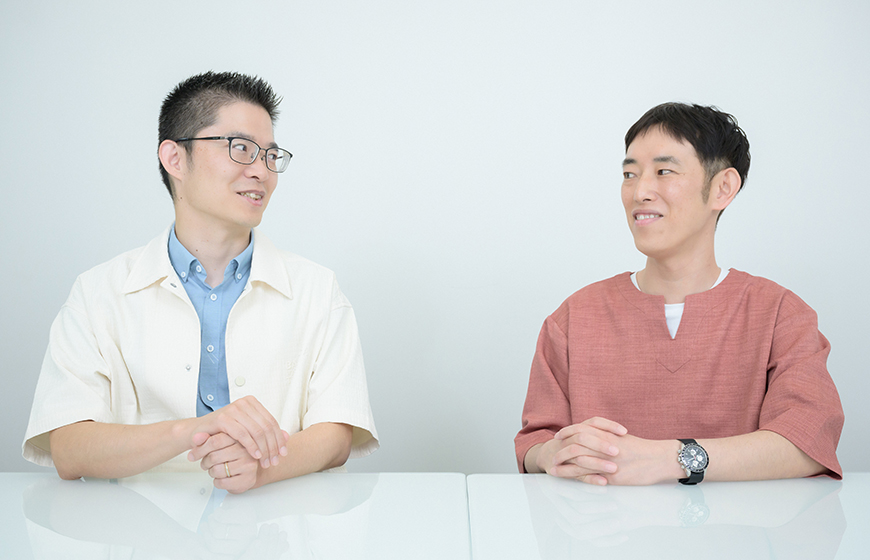
取材・文=グレタケ 武田敏則
※所属組織および取材内容は2025年7月時点の情報です。
※略歴内の情報は2025年10月時点での内容です。
1

STRATEGY
【後編】未来の“はたらく”を変革する——パーソルホールディングス×パーソルクロステクノロジー 両本部長が語る、AI戦略と共創の最前線
2

PROJECT
わずか10カ月で開発・導入を実現。データドリブンなタレントマネジメント基盤を形にした舞台裏
3

PROJECT
課題の本質をとらえ、伴走型の支援を―コンサルティング×テクノロジーで拓く、地域共創の最前線
4

PROJECT
生成AIによって「女性のはたらき方」が変わり始めた―クラフター小島氏×パーソルテンプスタッフ朝比奈対談
5
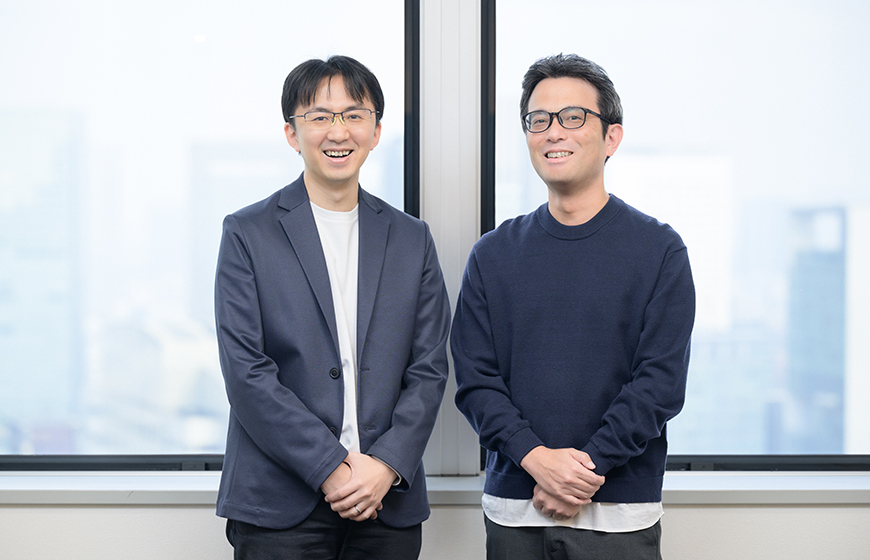
PROJECT
30を超える基幹システムを“無風”でクラウドに。パーソルテンプスタッフが挑むアプリリフト