PROJECT
国内38社6万人の業務基盤を支えるビジネスITアーキテクト部が挑む業務改革とは?

テクノロジードリブンの人材サービス企業を目指すパーソルグループ。今回は、CoE組織での横断支援から、情報システム領域の運用最適化にフィールドを移した山田に、現在の仕事とはたらく魅力について聞きました。
新卒で入社した当初は、「安定した仕事に就いて、長くはたらければいい」と漠然と考えていました。ところが社会全体でITが急速に普及し、社内でもパソコン活用が進むのを目の当たりにして、はたらき方そのものを変える力に衝撃を受けたんです。
それまでは、紙と電卓で一生懸命に計算していたのが、Excelに数字を入れるだけで瞬時にシミュレーションできる。この仕組みを理解できれば「自分の可能性を広げられる」と感じました。
とはいえ、いざIT関連の教本を読んでも、まったく理解できず、答えを見ても「日本語を聞いているのか?数字を聞いているのか?」と混乱するほどでした。でも、その「分からなさ」がかえって面白く、理解できるようになりたいと強く思ったんです。
この原体験が、ITを軸にキャリアを築いていこうと決意する転機になり、思い切ってIT業界へ飛び込みました。
未経験で転職した物流系のシステム会社では、ちょうど「2000年問題」の対応に揺れている時期で、大規模なシステム刷新が進んでいました。プロジェクトは混乱続きでしたが、それ以上に「世の中は、こんなにも一気に変わるのか」という衝撃が大きかったですね。
この経験から「IT領域はもっと面白くなる。もっと深く関わっていきたい」と考え、それは今でも変わりません。
現場からの抵抗は当然あるものだと思っています。ITは革新的であるべきですが、いきなり受け入れられることは少なく、新システムを導入すれば「自社には合わない」「前の方が良かった」といった声も出ることは理解しています。逆の立場になれば、自分もそういうこともあるでしょうし。
それでも、使い続けるうちに徐々に馴染んできて、数年後には業務に欠かせない存在になっていくケースも経験してきました。導入当初は強く反対していた人が、リプレイスの段階になると「残してほしい」と言うこともあります。
これまで物流・流通・販売など、幅広い業界に携わってきましたが、会社ごとに文化やカラーが違っても、定着のプロセスは共通しています。だからこそ私は、効果をどう実感してもらうかを何より重視しています。
2023年度にグループテクノロジー推進本部が立ち上がった際に、私はPMOという立場で参画しました。ちょうど、IT施策を支援する人材をプールし、グループ各社を支援するCoE組織の仕組みを整えるタイミングでした。
当時の上司に言われた「将来的にPMOという役割が不要になるくらい、自走できる強い組織をつくりたい」という言葉に、強く共感したのを覚えています。支え続けなければ成り立たない仕組みは健全ではないですからね。
結果的に、CoE組織は100名規模の体制へ拡大し、自ら考えて動ける組織へと成長していきました。その姿を見て、「自分はどこで価値を発揮すべきか」と、改めて考えるようになったんです。
そのとき思い浮かんだのが、これまでの経験をもっとも活かせる、グループ全体の情報システムを支える「ビジネスITアーキテクト部」でした。ここなら、自分のキャリアをさらに広げながら、グループの成長に貢献できると確信し、異動を決めました。
対象範囲はグループ全体へと広がりましたが、「社内の情報システム部門」という立ち位置は変わらないと捉えています。
ただ、一般的な会社では、情報システム部門が、会計・人事・販売管理などの基幹システムから、PCやスマホのデバイス管理、セキュリティ、ITコスト、戦略、ガバナンスに至るまで、あらゆるIT領域を担います。
一方で、パーソルグループほどの規模になると、すべてを一つの部署でカバーするのは現実的ではありません。私が室長を務めるコーポレートEX室では、財務系システムを中心に、法務・監査・総務、そしてグループポータルなどを担当しています。
業務領域としては、導入後に期待した効果を発揮できるよう、継続的なメンテナンスや改善を行う。また、役目を終えたシステムのリプレイスや廃止まで、責任を持って対応しています。
範囲や領域を限定することで、より深く入り込み、専門性を発揮して支える役割にシフトしています。
グループ各社はそれぞれ独立した法人であり、たとえ同じシステムを導入していても、使い方や定着度合いに差があります。そのため、現場のリアルな声を聞かなければ実態は見えてきません。この点は、これまで携わってきた会社と比べて、もっとも大きくスタンスを変える必要がありました。
また、各社の事情を尊重しつつも、グループとしての全体最適を追求する。この落としどころを探る調整力こそが、パーソルグループならではの難しさであり、同時にIT戦略をグループで推進していく醍醐味だと感じています。

2024年度まで3つに分かれていた室を統合したコーポレートEX室では、異なる文化や業務の進め方の違いが混在していました。現在は、その違いを一つひとつ整理し、共通化できるものはルールとして定着させることで、より安定した運用体制へと整えつつあります。
これまで複数の会社で社内システムに携わり、異なる文化やプロセスを数多く見てきたからこそ、「なぜ違いが生まれるのか」を客観的に捉えられています。
そうした違いを整理し、運用の共通化を進めるうえで、特に大事にしているのは、メンバーが積み重ねてきた努力を尊重し、その強みを活かして全体最適へとモチベートしていくことです。
これまでの知見を土台に、より大きな規模と高い視点で成果を求められる今の環境は、とてもやりがいがあり、楽しみながら取り組めています。
システム向き合いの仕事は「止まらないのが当たり前」で、成果が表に出にくい領域です。しかし裏を返せば、それだけ組織から強い期待を受けている証でもあります。そうした世界にいられるのは、すごく幸せだと思いますね。
現在は約60のシステムを管理しており、直近では新システムの初期リリースにも携わり、無事に終えています。扱うシステムの種類も多岐にわたるからこそ、改善すべき点や新たな挑戦の余地は常に見えてきます。
課題が尽きない環境は決して楽ではありません。しかし、それだけ挑戦と成長の機会にあふれていることが、この領域の大きな魅力だと思います。
そうですね。多くの企業における情報システム部門の役割は「システムを正常に稼働させること」が最大のミッションです。会社によっては、最低限の稼働を維持することが最優先で、余計な提案はコスト増と見なされ、歓迎されない側面とされる場合もあります。
しかしパーソルグループは違います。安定稼働は当然として、その先に「どのように進化させ、価値を高めるか」が常に問われます。新しい仕組みや改善策を積極的に提案することが求められ、ITが担うべき役割への期待の高さを実感しています。
まず大前提として、「自分の考えが常に正しい」とは思っていません。違和感を覚える施策があったとしても、それには必ず背景や事情、何らかの制約があるはずです。そのため、一度は「考え抜かれた結論」として受け止め、自ら歩調を合わせることを大切にしています。
そのうえで、見落とされている点や改善の余地を感じたら、自分なりに考えて、提案していけばいいと思っています。

「室」という単位にこだわらず、部署全体でAIやテクノロジーを積極的に活用し、新しいシステム運用へと発展させていきたいと考えています。
これまでグループ横断で多様な基幹システムを運用してきましたが、限られた人員やタイトな期限といった制約の中で、目の前の課題に対応し続ける「守り」が中心でした。
しかし、いまは状況が大きく変わりつつあります。これからはグループ全体でリソースを循環させ、システムを通じて現場の生産性やはたらきやすさを高め、より直接的に貢献していきたいですね。
これまでは事業の「成長・拡張」を優先してきましたが、これからはシステムや運用そのものを見直し、最適化していくことも重要だと捉えています。
ただ、やめる判断は簡単ではありません。全体最適のために停止すべきシステムであっても、現場では日常業務に浸透していることも多く、合理性だけでは割り切れない難しさがあります。
何を広げ、何を絞るかを見極める「選球眼」を磨く必要がある。そうした判断ができる組織になることで、結果的にシステムや運用の価値も、より明確に見えてくるはずです。
一番の魅力は、はたらく場所もキャリアも、自分の意思で選べる環境が整っていることです。
テレワークはすでに文化として根付いており、出社か在宅かを柔軟に選択できます。また、コーポレートEX室には、住む場所の制約がない「フルリモート勤務」で活躍しているメンバーもいます。
もちろん、その分オンラインでのコミュニケーション力は欠かせません。情報を正確に伝え、タイムリーに共有する意識は必要です。しかし、それさえできれば自由度が高く、自律的にはたらける環境が整っています。
さらに、キャリア形成の選択肢が豊富なのもパーソルグループの特徴です。キャリアチャレンジ制度や*¹キャリアスカウト制度*²を使えば、グループ内で新しい職種や部署に挑戦できます。実際、私もこの制度を活用して今の部署へ異動しました。
スキルや経験に応じて、グループ全体の中から自分の活躍の場を選べる。これはパーソルグループならではの強みです。だからこそ、意欲ある人にとって、可能性を最大限に広げられる場所だと感じています。
*1 キャリアチャレンジ制度:グループ全社の社員を対象にした、グループ会社間での公募型異動制度
*2 キャリアスカウト制度:社員が経歴や異動意向を社内システムに登録するとグループ内の他部署から直接スカウトを受け、異動することができる制度
技術力そのものも大切ですが、それ以上に「システムは、ちゃんと使われてこそ価値がある」という視点を持てることが重要だと考えています。
AIやデータ活用に長けたエンジニアは、非常に頼もしい存在です。それと同時に、テクノロジーを現場に根づかせ、成果に結びつける力も問われています。
技術はあくまで手段にすぎません。目指すのは、「業務をより良くすること」と「はたらく人の幸せを実現すること」です。その目的に向かって、自分の専門性をどう活かせるかを考え、実行できる方と一緒に挑戦していきたいですね。
取材=伊藤秋廣(エーアイプロダクション)/文=嶋田純一/撮影=山本嵩
※所属組織および取材内容は2025年10月時点の情報です。
※略歴内の情報は2025年10月時点での内容です。

パーソルホールディングス株式会社
グループAI・DX本部 ビジネスITアーキテクト部
コーポレートEX室
室長
1997年、新卒で大手給食受託運営会社に入社し、新規営業を担当。1999年以降、SIerでの物流・流通系システム開発、プリセールスや営業を経て、複数の事業会社で情報システム部門の責任者を歴任。IT全般の運用管理からセキュリティ、ガバナンス管理まで幅広く経験。2023年にパーソルホールディングスへ入社し、現在に至る。
1

STRATEGY
【後編】未来の“はたらく”を変革する——パーソルホールディングス×パーソルクロステクノロジー 両本部長が語る、AI戦略と共創の最前線
2

PROJECT
わずか10カ月で開発・導入を実現。データドリブンなタレントマネジメント基盤を形にした舞台裏
3

PROJECT
課題の本質をとらえ、伴走型の支援を―コンサルティング×テクノロジーで拓く、地域共創の最前線
4

PROJECT
生成AIによって「女性のはたらき方」が変わり始めた―クラフター小島氏×パーソルテンプスタッフ朝比奈対談
5
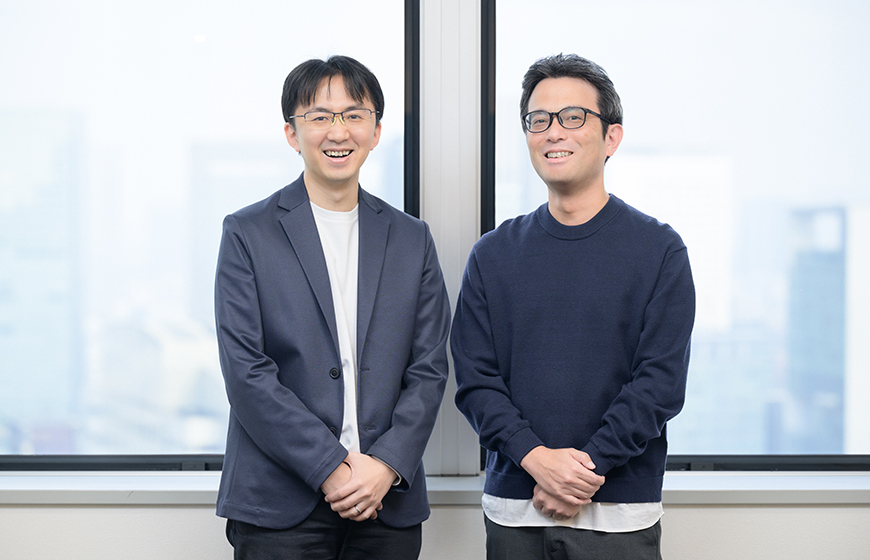
PROJECT
30を超える基幹システムを“無風”でクラウドに。パーソルテンプスタッフが挑むアプリリフト