PROJECT
「価値ある仕事に集中できる状態」を目指す―業務改善を文化へと育むプロジェクト

パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社
テクノロジーコンサルティング事業部
公共ソリューション統括部
統括部長
前職では大手SIerにて業務コンサルタントとして従事。コンサルティング経験を活かし、2017年に現パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社に中途入社。多業種でのBPR/RPA/AI/テレワークなどの導入および 育成/内製化支援に従事し、企業のDX推進や生産性向上に寄与。民間で培ったノウハウを活かし、現在は公共DX事業を立ち上げ事業責任者を担う。
パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社
テクノロジーコンサルティング事業部
公共ソリューション統括部
公共コンサルティング部
公共戦略推進グループ
課長
2019年に現パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社に中途入社。国際回線NW保守やデリバリー部門の品質および業務プロセス改善を担当。以降、RPA開発~プロジェクトマネジメント、研修講師など幅広い支援経験を活かし、RPA/DX推進コンサルティングに従事。
その後、パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社にて、公共事業部の立ち上げ経験を経て、全国自治体の課題やニーズのヒアリングから公共DXの営業提案まで一気通貫で担当し、複数の公共事業にプロジェクトマネジャー、品質管理およびアドバイザリーとして参画。
パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社
テクノロジーコンサルティング事業部
公共ソリューション統括部
公共コンサルティング部
コンサルティング第1グループ
コンサルティング第1チーム
食品卸売会社へ新卒入社し、労務、研修企画を中心とした人事・総務業務を経験。2023年にパーソルワークスイッチコンサルティング株式会社へ転職し、大手銀行における金融商品廃止プロジェクトPMO支援や、地方自治体における女性活躍推進に関する調査・企画を担う。
テクノロジーの力で女性一人ひとりのキャリアを支援し、地域や企業の変革を後押ししたい―そんな思いから始まったのは、パーソルワークスイッチコンサルティングと岡山県真庭市による「女性活躍推進プロジェクト」です。本プロジェクトでは、現地に根ざした調査を起点に、真に求められる支援のあり方を模索しています。
今回は、現地で奔走しながらプロジェクトを推進してきた、事業責任者の水野、プロジェクトマネジャーの安藤、コンサルタントの齊藤の3名に、取り組みの背景や地域のリアルな声、そして今後に描く未来について話を聞きました。

水野
岡山県真庭市は、人口およそ4万人の自治体で、「消滅可能性都市」にも指定されており、特に若い女性の流出が深刻な課題となっています。進学や就職を機に市外へ出た後、そのまま戻らない。こうした状況を変えたいという想いが、今回のプロジェクトの出発点です。
パーソルワークスイッチコンサルティングでは、2022年から岡山県内の自治体に対して、「専門人材の派遣」「職員向け研修の実施」「相談窓口の設置」など、テクノロジーを活用した現場密着型の支援を継続してきました。
行政支援で培ってきた知見と、岡山県での取り組みを通じて深めた地域理解をもとに、今回は真庭市と連携し、「女性活躍推進プロジェクト」を進めることになりました。

安藤
この事業を通じて、真庭市の女性が活躍するために、「誇りをもって」暮らすことができる「魅力」ある真庭にするために必要な要素を調査する必要がありました。
特に、出産や子育てといったライフイベントを経てもキャリアを継続しやすい仕組みや、柔軟なはたらき方を実現するために必要なスキル獲得に関する真庭市民のリアルな声を集めることを重要視しました。

安藤
これまで実施してきた岡山県とのプロジェクトでも、私たちは現地に足を運び、現場ではたらく方々と対話を重ねながら支援を行ってきました。
今回の真庭市との取り組みも、単なるコンサルティングにとどまらず、「現場に入り込み、課題を一緒に解いてくれる存在」として、信頼を寄せていただいていると感じています。

水野
実際にこれまで関わった自治体の方々から、「ここまで主体的に動いてくれるとは思わなかった」と言われることもあります。
もちろん実績やノウハウも重要ですが、自治体の皆さんと信頼関係を築きながら、どこまで当事者意識を持って寄り添えるかが重要だと考えています。

安藤
公共事業は、多くの提案が紙ベースで行われ、一度のプレゼンや資料で採択が決まるという厳しい世界です。
だからこそ私たちは、単に要件をなぞるのではなく、「このプロジェクトをどう成功に導くか」「どれだけ本気で取り組むのか」という“想い”や“覚悟”を、資料や言葉に込めて伝えることを重視しています。
仮に不採択になった場合でも、「これ以上はできなかった」と納得できるような120%の提案をする。公共領域はそれほどシビアですが、その分、やりがいも非常に大きいと感じています。


安藤
最初に取り組んだのは、真庭市が抱える課題の本質を捉えることでした。
当初、真庭市からは「ITスキルが学べる講座のニーズを調査したい」といった要望がありました。この要望を受け、まずは地元の方々の現状や声をしっかりと拾い上げる「調査」に重点的にリソースを投じるべきだとご提案し、市と何度もすり合わせを重ねながら進めていきました。

齊藤
具体的には、真庭市に暮らす人たちがどのようなキャリア意識や就労ニーズを持っているのか、また受け入れ側となる企業が抱えている課題を、それぞれの視点から調査しました。
実際の調査には、「アンケート」「インタビュー」「座談会」の3つの手法を組み合わせています。
アンケートでは、広く実態を可視化し、インタビューでは一人ひとりの背景や想いを深掘りしました。さらに、高校生や子育て中の方など、同じ立場の人が集まる場では座談会を開催し、言葉になりきらない空気感までくみ取ることを意識しました。

齊藤
調査を進めるうえで、企業の接点となるリストはなく、私たち自身で一件一件調べていく必要がありました。市とも連携を取りながら進めていましたが、情報共有やリソースの制約もあり、調査対象の設定には試行錯誤がありましたね。
ただ、現地に足を運ぶうちに、「あそこの方に話を聞いてみるといいよ」「うちの学校にも来て」といった声をかけていただけるようになり、真庭市の皆さんの温かさに何度も助けられました。
そうしたつながりの中で、少しずつ地域の方々との信頼関係が築かれ、結果として、表層的ではない「本音の声」を聞くことができたと思っています。

水野
齊藤さんは、市内の中学校や高校、大学、企業など、あらゆる現場に自ら足を運び、何十回にもわたるヒアリングや座談会を実施してくれました。その姿勢と行動力が、今回のプロジェクトを支える大きな原動力になったと感じています。

齊藤
周囲に心配されるほど、何度も真庭に足を運びました(笑)。
というのも、お二人が提案資料やプレゼンに込めたパッションを間近で見て、「想いはこうやって伝えるんだ」と強く感じたからです。だからこそ、私も同じように熱意を持って全力で向き合うよう心がけていました。
このお客様に対する強い想いは、どのプロジェクトでも変わらず、部署の枠を超えて根づいている、私たちのカルチャーだと思います。


齊藤
調査前は、「就労していない女性が多く、自分の理想のはたらき方をどこかで妥協しているのではないか」という仮説を立てていました。しかし、実際に現地で多くの方と対話を重ねる中で、その印象は覆されたんです。
市民側の調査では、共働き世帯が予想以上に多く、「ITスキルを基礎から学びたい」「もっと活用できるようになりたい」といった前向きな声が数多く寄せられました。
一方で企業側からは、「AI技術に関心がある」といった声があるものの、テクノロジーを活用した柔軟なはたらき方の整備は、まだ十分に進んでいないという現状が見えてきました。
今回の調査を通じて、「市民の意欲」と「企業の受け入れ体制」との間にあるギャップが明らかになってきたんです。

齊藤
現在、大きく2つの軸で施策を構想しています。
ひとつ目は、「ITスキルを身につける学びの仕組みづくり」です。まずは社内業務の効率化や業務改善に直結する“インプット型”の講座を設計し、さらにその後には、職場ですぐに活かせる“ワークショップ型”の応用講座へとつなげていく流れを想定しています。
ふたつ目は、「企業側の受け入れ体制の強化」です。特に地方では、「デジタル=テレワーク」といった先入観が根強く、導入を自分ごととして捉えにくい企業も多く見受けられます。
そうした誤解を丁寧に解きほどきながら、経営層や管理職の方々に向けて、「デジタルの活用こそが、人材確保や組織改革に直結する」という視点を、しっかり届けていきたいと考えています。
また、真庭市内には既にフリーランスとして活躍する方を育成するための、デジタルに特化した民間講座を実施していることも確認できました。こうした既存の取り組みとも連携も視野に入れて、地域全体のはたらき方の選択肢を広げていければと思います。

水野
私たちには、デジタル人材の育成に特化した「Work Switch +DIGITAL」という独自のサービスがあり、数多くの研修・育成を支援してきました。中でも人事DXの領域では、組織開発や人材戦略に深く関わりながら、制度設計から運用までを支援しています。
もう一つ大切にしているのが、「伴走型」の支援スタイルです。現場に足を運び、地域の方々や企業と直接向き合い、課題の本質を見極めながら解決策を一緒に形にしていく。その後の実行フェーズを、どう支え続けられるかを常に意識しています。


水野
テクノロジーを活用できるようになることで、地方にいながらはたらく選択肢は大きく広がります。
特に今後は、テレワークをはじめとした柔軟なはたらき方がさらに多様化し、デジタルスキルを持つ人材ほど、地域にいながら最前線で活躍できるようになっていくと思います。

安藤
行政や企業の支援体制も徐々に整い始めており、テクノロジーの活用によって、学びの選択肢や支援の形はもっと広げられると考えています。その実現によって、「地方に定住しながらキャリアを築く」という選択が、より自然なものになっていくはずです。
そして、誰もが「自分らしくはたらきながら人生を築ける社会」になれば、少子化という社会課題も解消されるのではないでしょうか。
テクノロジーやはたらき方がここまで進化したからこそ、私自身も管理職としてのキャリアを積み重ねてくることができました。その実体験があるからこそ、できないことはないと本気で思っています。

齊藤
真庭市には、温かく前向きな方が多く、木材加工をはじめとする地場産業や、豊かな自然などの資源があります。だからこそ、適切な打ち手を講じていけば、地域全体を活性化できると確信しています。
今回の調査を通じて、市民や企業のリアルな声をたくさん聞いてきました。次はその声をもとに、よりはたらきやすく、住みやすい環境を整え、「真庭市で暮らしたい、はたらきたい」と思ってもらえるような未来を実現していきます。

齊藤
私自身、子育てしながら第一線で活躍されている水野さんや安藤さんの姿を間近で見て、強い希望をもらっています。
「女性だから」「男性だから」ではなく、一人ひとりが「やりたいことに挑戦できる社会」にしていきたい。そうした環境を、真庭市を起点に全国へと広げていけたらと思っています。

安藤
若者が進学や就職を機に都市へ流出していく。この大きな流れをすぐに変えるのは難しいかもしれません。
しかし、地域での「暮らしやすさ」や「はたらきがい」といった本質的な魅力を整え、「この地域だからこそできる仕事」を生み出していくことが、選ばれるまちづくりの第一歩だと感じています。
実際に、地元の高校生からは「真庭が好き。でも、将来の仕事を考えると残るのは難しい」といった声もありました。現地で何度も対話を重ねてきた私たちだからこそ、そうした市民の“ラスト1マイル”のリアルな声を、しっかりと国にも橋渡ししていきたいと思います。

水野
女性や地域の方々が、自らの価値を再発見し、はたらくことを通じて新たな可能性を拡げていける。そんな機会や仕組みを増やしていくことが、私たちが地域とともに歩むうえでの使命だと捉えています。
日本が抱える社会課題は決して小さくありませんが、一人ひとりの可能性に光を当て、地域からもう一度元気を取り戻していきたいですね。

取材=伊藤秋廣(エーアイプロダクション)/文=嶋田純一/撮影=PalmTrees
※所属組織および取材内容は2025年11月時点の情報です。
※略歴内の情報は2025年10月時点での内容です。
1

STRATEGY
【後編】未来の“はたらく”を変革する——パーソルホールディングス×パーソルクロステクノロジー 両本部長が語る、AI戦略と共創の最前線
2

PROJECT
わずか10カ月で開発・導入を実現。データドリブンなタレントマネジメント基盤を形にした舞台裏
3

PROJECT
課題の本質をとらえ、伴走型の支援を―コンサルティング×テクノロジーで拓く、地域共創の最前線
4

PROJECT
生成AIによって「女性のはたらき方」が変わり始めた―クラフター小島氏×パーソルテンプスタッフ朝比奈対談
5
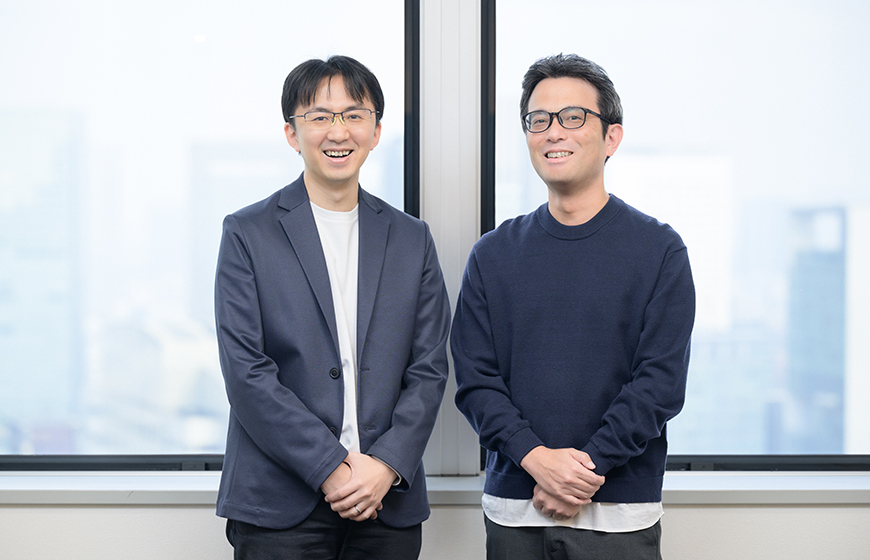
PROJECT
30を超える基幹システムを“無風”でクラウドに。パーソルテンプスタッフが挑むアプリリフト