PROJECT
国内38社6万人の業務基盤を支えるビジネスITアーキテクト部が挑む業務改革とは?

パーソルホールディングス株式会社
グループAI・DX推進本部
ビジネスITアーキテクト部
HR-DX室
リードコンサルタント
大手ERPおよび国内タレントマネジメントシステムの導入コンサルタントを経て、2024年4月にパーソルホールディングスへ入社。社内ITコンサルタントとして主にHR部門の業務DXを推進。現在は、グループタレントマネジメントシステムの開発プロジェクトにてプロジェクトマネージャーを務め、プロジェクト全体および開発体制のリードを担っている。
パーソルホールディングス株式会社
グループAI・DX推進本部
ビジネスITアーキテクト部
HR-DX室
リードコンサルタント
前々職にて基幹システムの導入コンサルタントとして、運用・保守までを経験。前職の株式会社パーソル総合研究所では、タレントマネジメントシステムの導入に従事。2024年4月にパーソルホールディングス株式会社へ転籍し、グループ共通タレントマネジメントシステムの導入推進をリードし、現在に至る。
社員のMBO(目標管理制度)や評価を一元管理するために開発された、パーソルグループのタレントマネジメントシステム「CareerPolaris(キャリアポラリス)」。多様な人事制度や運用に対応しながら、開発と導入を1年足らずで進めた異例のプロジェクトでした。
今回は、プロダクトオーナーとしてシステムを形にした設楽と、現場での導入をリードした後藤にインタビュー。数々の困難をどう乗り越え、プロジェクトを前進させてきたのか――その挑戦の軌跡を追いました。

設楽
パーソルグループは中期経営計画2026で、「多様な人材が“はたらくWell-being”を体現し、価値創造を推進する組織へ」といった目指す姿を掲げています。その実現には次世代経営層の育成や、人材配置の最適化を見据えた人事運用の高度化が欠かせません。
しかし当時は、グループ各社が独自にMBOを運用し、使用ツールもバラバラでした。そこで、「データドリブンな人事運用」を実現するため、グループ全体で情報を一元管理できる基盤整備が急務となっていたんです。

設楽
当初は、パーソル総合研究所が提供するタレントマネジメントシステム「HITO-Talent」を、共通基盤として展開する構想が進んでいました。しかし、HITO-Talentの事業撤退が決まり、タレントマネジメントの仕組みを再検討する必要が生じたんです。
その際、外部サービスも含めて検討しましたが、グループ各社の多様な制度や運用に柔軟に対応するには、既存のサービスでは限界がありました。
そうした背景から、HITO-Talentで培った知見と最新のテクノロジーをかけ合わせた、新たなタレントマネジメントシステムの開発プロジェクトがスタートしました。

設楽
今回のプロジェクトでは、ビジネスオーナーは人事側が担い、IT部門と人事部門が密に連携しながらプロダクトを形にしていく体制を取りました。
タレントマネジメントは、運用現場と密接に関わる領域です。だからこそ「IT部門がつくり、人事部門が使う」という分業ではなく、同じ目的を共有する“ひとつのチーム”として動くことを大切にしていました。

後藤
設楽さんと私は、もともとパーソル総合研究所でHITO-Talentの導入支援を担当していました。しかし事業の撤退が決まったタイミングで、「グループ全体のタレントマネジメントシステムを立ち上げる構想があるけど、興味ある?」と、パーソルホールディングス側から声をかけてもらったんです。
迷う間もなく「やってみたい」と思い、パーソルホールディングスに転籍し、本格的な実行フェーズから参画しました。


設楽
最大の課題は、想定を超える短期間で、計画を実現しなければならなかったことです。
当初は2024年度中の開発を想定していましたが、実際にはその期間内に導入まで完了させる必要がありました。さらに開発チームの体制が整い、本格的に開発が始動したのは6月でした。
そのため、開発から導入までをおよそ10カ月でやりきるという、非常にタイトなスケジュールだったんです。

設楽
HITO-Talentの導入を進めていた段階で、2025年4月のシステムリリースをマイルストーンに掲げていました。そのため、スケジュールを後ろ倒しにすることはできなかったんです。

後藤
グループ各社の中には、他社のタレントマネジメントシステムを検討しているところもあり、期限の延長は難しいという空気を感じました。
非常に厳しいスケジュールでしたが、ここで対応が遅れれば、グループ全体で共通基盤を整備するという構想自体が崩れてしまう。だからこそ、前に進む以外の選択肢はありませんでした。

設楽
もっとも効果的だったのは、早い段階で開発範囲を見直し、優先度の高い機能に絞って段階的にリリースする方針へ切り替えたことです。
もちろん、一部機能とはいえ、告知していたリリース計画を変更するのは信頼関係にも関わるため、容易ではありません。それでも、プロジェクトを成功させるには避けて通れない決断だったと思います。
「この機能なら半年後でも問題ありませんか?」「必須でない部分は来年度以降に回しましょう」といった調整を重ねながら、地道に前進させていきました。

設楽
システム開発に携わるのは初めての経験で、特に「仕様を決める」という工程の難しさを痛感しました。
開発初期は、人事担当者やデザイナーと毎日のように集まり、モックアップをつくるところからスタートしました。しかし、「この画面が本当に最適なのか」「使う人にとって分かりやすいのか」と、自問しながらの試行錯誤が続きました。
UI/UXには一定のセオリーはありますが、実際の使われ方や感じ方に“正解”はありません。そのため、多様な意見を一つひとつ整理しながら、意思決定を重ねていく責任の重さを強く感じました。


後藤
各社への導入は、まずシステムを使わずにMBOを運用していた小規模組織から着手しました。既存運用との比較がなく、導入のハードルが低かったという背景もあります。
具体的には、導入スケジュールを提示したうえで、各社の現行業務を丁寧にヒアリングするところから始めました。ただ、当初はまだ画面や仕様書が無かったので、現行業務をドキュメントに洗い出し、開発後に初期設定し実際の画面を確認しながらすり合わせを進めました。
システムがない状態での導入支援は、前例のない取り組みです。ただ、これまでの経験を活かし、密な対話を重ねながら丁寧に進めたことで、スムーズな展開につながったと感じています。

後藤
もっとも苦労したのは、事前にアナウンスしていた「HITO-Talentと同等のシステム」という表現が、想像以上に幅広く受け取られていたことです。
「同等」と言っても、「同じ機能がある」「同じことができるようカスタマイズされている」「UIや操作感までまったく同じ」など、人によって受け取り方はまったく異なります。
特に、HITO-Talentを深く使い込んでいた会社ほど、その認識の差を埋める説明や調整に時間を要しました。この経験を通じて、伝え方の精度がいかに重要かを痛感しました。

後藤
導入先によって人事体制やその規模も異なるため、進め方を一律にせず、それぞれの状況に合わせて柔軟に対応してきました。特に、不満や懸念の声が上がった際には、まず相手の話に耳を傾け、きちんと受け止める姿勢を心がけています。
また、グループ全体への導入という性質上、一方的な指示と受け取られないよう、コミュニケーションの取り方にも注意を払いました。一方的にお願いするのではなく、できる限り要望に応える努力をすることで、「この前は聞いてくれたから、今度はこちらが頑張ろう」と思ってもらえる関係性を築けたと思います。
そうした小さな信頼の積み重ねが、結果として厳しいスケジュールの中でも前に進む力になったと感じています。

設楽
一部機能のリリース時期を見直した際も、各社がスムーズに受け入れてくれたのは、後藤さんたちのきめ細やかな対応のおかげです。本当に感謝しています。

後藤
プロジェクト開始時の導入担当は、私ひとりでした。さらに別のプロジェクトも兼任しており、実質は“半人分”でスタートしたような状況です。しかし、システム完成後は、各社の要件に応じた初期設定や細かな調整が必要となり、負荷は一気に高まります。
このままでは対応しきれないと判断し、上司に掛け合い、別部門から1名をアサインしてもらい、さらに配属されたばかりの新人メンバーにも加わってもらいました。そのメンバーについても1on1を通じて育成を進めながら、それぞれが役割を持って導入対応を進められています。


後藤
正直なところ、原動力は「やるしかない」という覚悟でした。すでにリリース時期を公表していた以上、途中で止めるという選択肢はありません。「決まっているからこそ、何があっても間に合わせる」――その一心で動いていました。

設楽
開発中は、仕様に確信を持てないまま判断を迫られる場面の連続でした。それでも、「こうしたい」という想いにデザイナーやエンジニアが真摯に応えてくれる。自分の意図が、プロダクトとして形になっていく過程は、とても刺激的でした。
体力的に厳しい時期もありましたが、それ以上に、「システム開発って、こんなに面白いんだ」と感じられたことが、いちばんの原動力になっていたと思います。

後藤
初めて取り組んだ新人教育では、正解のない中で一緒に悩み、考え、試行錯誤を重ねる日々でした。気づけば、苦労を分かち合う“戦友”のような絆が生まれ、それが自分にとっても大きな支えになっています。
振り返ると、どんなに厳しい状況でも「諦めずに、周囲を巻き込みながら前に進むこと」が道を拓く。そのことを、身をもって実感したプロジェクトでした。

設楽
このプロジェクトを通して改めて感じたのは、「仕事は決してひとりでは成り立たない」ということです。特にエンジニアの方々は、まさに“スーパーエンジニア”と呼びたくなるほど優秀で、業務委託という形の強みを最大限に活かせたと考えています。
この短期間でプロダクトを形にできたのは、多くの方の惜しみない協力があったからこそです。この場を借りて、プロジェクトに関わってくれた方に、改めて感謝を伝えたいと思います。

後藤
私自身、もともとタレントマネジメントの領域に深く関わりたいという想いでパーソル総合研究所に入社しました。ただ、これまではシステムを“提供する側”としての関与に留まり、導入後の運用や変化にまで踏み込めないもどかしさがあったんです。
今回のプロジェクトでは、その「提供の先」まで携われていることに、大きなやりがいを感じています。
今後は、導入という“種まき”を継続しながら、グループ全体にタレントマネジメントを根づかせていくことが目標です。そして、その先で、社員一人ひとりのキャリアを支える仕組みへと育てていくことを目指していきます。

設楽
プロダクトオーナーとして、最終的な意思決定と責任は自分にあるという意識を常に持っています。「CareerPolaris」の仕様は、その判断の積み重ねの結果です。だからこそ、現場の声をしっかり受け止め、これからも自ら改善をリードしていきます。
初めてシステム開発に深く関わったことで、この領域の奥深さと可能性を実感しました。今回得た経験を糧に、今後も新しい挑戦に積極的に関わりながら、自分自身も成長し続けていきたいと思います。

取材=伊藤秋廣(エーアイプロダクション)/文=嶋田純一/撮影=長坂佳宣(PalmTrees)
※所属組織および取材内容は2025年11月時点の情報です。
※略歴内の情報は2025年10月時点での内容です。
1

STRATEGY
【後編】未来の“はたらく”を変革する——パーソルホールディングス×パーソルクロステクノロジー 両本部長が語る、AI戦略と共創の最前線
2

PROJECT
わずか10カ月で開発・導入を実現。データドリブンなタレントマネジメント基盤を形にした舞台裏
3

PROJECT
課題の本質をとらえ、伴走型の支援を―コンサルティング×テクノロジーで拓く、地域共創の最前線
4

PROJECT
生成AIによって「女性のはたらき方」が変わり始めた―クラフター小島氏×パーソルテンプスタッフ朝比奈対談
5
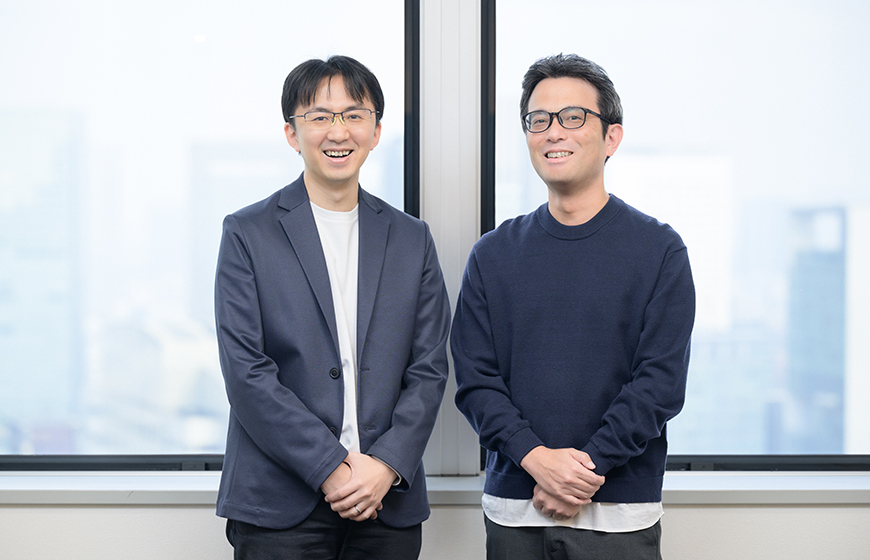
PROJECT
30を超える基幹システムを“無風”でクラウドに。パーソルテンプスタッフが挑むアプリリフト