OTHER
CoEの内製開発エンジニアチームとは?

パーソルホールディングス株式会社
グループAI・DX本部 デジタル開発部
テクニカルアライアンス室
室長
2009年中堅SIer企業入社。SEとしてさまざまな請負案件を実施。2017年パーソルプロセス&テクノロジーに入社後、グループ向け基幹サービスの開発保守運用や、データ利活用基盤の開発などに従事。2025年4月より現職。
パーソルホールディングス株式会社
グループAI・DX本部 デジタル開発部
SBUデジタル開発室
エンジニア
2024年にパーソルホールディングスへ中途入社。テクロノジーによる事業ドメインへの価値創出に貢献するプロダクト開発に従事。また、業務上の連携円滑化を主目的としたコミュニケーションの活性化を行い、より自身の「はたらく」との整合を見出す活動を推進中。
パーソルホールディングス株式会社
グループAI・DX本部
デジタル開発部 SBUデジタル開発室
エンジニア
新卒でSIerへ入社。CRM製品の導入・運用や、製造業でのソフト開発を経験し、2023年にパーソルホールディングスへ入社。CoEの一員として、グループ個社の支援を開発の面から行う。また、Tech Harborの一員として、開発標準化にも積極的に取り組み中。
2023年4月、パーソルホールディングスのCoE(Center of Excellence)内にプロダクト開発チームとして「SBUデジタル開発室」が組成されました。CoEとして行うグループ各社への技術支援の取り組みにおいて、内製開発の推進や技術的な知見をもとにした提言を行うといった活動の傍ら、「Tech Habor」と名付けたエンジニアがはたらきやすい環境づくりにも取り組んでいます。
今回は「Tech Harbor」のメンバーである佐藤、黒木、大坪の3名に、「Tech Habor」プロジェクトが始動した背景や、どのような内製開発組織を目指しているのかについて聞きました。

佐藤
前職は中堅SIerでSEをしていました。スキルが上がるにつれ、より規模が大きい仕事に挑戦したいと思うようになりました。
その後、パーソルプロセス&テクノロジーへ転職し、パーソルグループ全体で利用する業務システムの開発に取り組んでいました。そんな中、パーソルホールディングス内に新たに内製開発組織をつくるという話を耳にして、新たなチャレンジができるのではないかという思いから2023年10月にパーソルホールディングスへ転籍しました。

大坪
2019年に新卒でSIerに入社し、CRM製品のパッケージ導入におけるサポート業務を担当していました。コンサル寄りの仕事だったため、自ら手を動かしたいという思いから別のSIerに転職。希望通り手を動かし、開発できる環境でしたが、開発における制限が多い会社でした。そこで、手を動かしながら提案にも関われる環境に身を置こうと考えました。
そんな時に見つけたパーソルホールディングスはちょうどテクノロジー活用に力を入れ始めたタイミングだったため、自らが望む環境を手に入れやすいのではないかと思い入社を決めました。

黒木
私は新卒でアンケートシステムを扱う会社に入社しました。その後、起業を含め複数の会社を経験したのですが、直近勤務していた会社は、定められた開発言語では自分が使いたい技術を使えないという状態が続いていました。
次第に、自らが興味・関心がある技術を活用しながら成長できる環境に身を置きたいと思うようになり、パーソルホールディングスへの入社を決めました。

黒木
決め手となったのは面接でしたね。パーソルホールディングスの面接は面談のような雰囲気で、私自身が何をしたいか、どうなりたいかを深掘る時間でした。終始話しやすい雰囲気で、「この人たちと一緒にはたらきたい」と強く思いました。

大坪
面接時に「これはできるよ」「これはできないけれど代わりにこんなことができる」など、私のやりたいことに対して丁寧な説明があり、入社後の業務イメージを持ちやすかったのが大きな理由です。エンジニア一人ひとりのやりたいことに寄り添ってくれる組織なのだと感じました。

佐藤
SBUデジタル開発室は、グループのデジタル化を推進していくために「パーソルグループをよりよくしていこう」というマインドと深い事業理解を持ちながら、アジャイルにプロダクト開発を行う内製開発組織です。
現在は10名が所属しており(2024年7月時点)、ほとんどが経験者採用で入社したエンジニアです。そのバックボーンはさまざまですが、私たちのようにSIerを経て入社される方や、レガシーな開発環境からモダンな開発環境を求めて入社する方が多いように感じます。
組織の方針として特徴的なのはそれぞれがフルスタックエンジニアを目指していることでしょうか。スクラム開発を採用しているため、それぞれができる技術領域が偏ってしまうと、メンバー間の相互の協力関係が築きにくくなってしまうのではないか、ということを懸念しています。
そのため本人の希望も聞きながら、前職では担当していなかった領域も積極的に担当してもらい、それぞれがなるべく広い領域をカバーできるようにしています。


佐藤
「Tech Harbor」はSBUデジタル開発室内で取り組んでいる、エンジニアがはたらきやすい環境づくりを推進するためのプロジェクトです。「テクノロジーによる事業ドメインへの価値創出に貢献する」ための礎をつくるべく、具体的には以下に取り組んでいます。

佐藤
CoEが本格的に始動し、SBUデジタル開発室としての活動が本格化していく中、再現性があるナレッジを蓄積していく必要性を感じました。各SBUへの技術支援の価値発揮を高めていくため、そしてスピード感を持って開発を行うためには、一定の要素を標準化した上でナレッジを蓄積し、共有できる状態をつくっていくべきだという結論に至りました。
そして、「何のために標準化をするのか?」というところを改めて言語化していく過程で、CoEのエンジニア組織である自分たちはどうありたいのかを考える取り組みに名前を付けることにし、誕生したのが「Tech Harbor」です。技術やプロセスが集まり、いつでも帰ってくることができるコミュニティの場となり、港から価値創造に向けて出発していくといった思いを込め、港を連想する名称にしました。

大坪
経営陣や上層部からの指示ではなく、メンバー間のアイデアによって自然発生的にプロジェクトが始動しました。誰かが旗振り役をしていたというよりは、全員が「やらないといけないよね」という認識を持っていた形です。


佐藤
2023年度中に外部コーチを交えてエンジニア組織として「ありたい姿」のロードマップを作成し、その後はロードマップを元に技術領域ごとに担当を決めて標準化に向けた作業を開始したところです。
まず取り組むべきは風土や文化、環境を言語化することだと思っています。それによってDeveloper Experience(開発者体験)を高めながら、「Tech Habor」の旗印とともにメンバー全員が一丸となって助け合いながら成長していこう、という雰囲気になっています。

佐藤
まずはパーソルホールディングスのDeveloper Experienceが高い状態を目指したいです。そこから、パーソルホールディングスだけではなく、パーソルグループ全体に「Tech Harbor」の輪を広げ、「Tech Harbor」を起点にアイデアやナレッジを蓄積し、新しい価値を生み出せるような世界を夢見ています。

大坪
私は高速開発基盤作りに興味があり、今後「Tech Harbor」内で取り組んでいきたいと思っています。開発環境を標準化することで、テンプレートを活用できる環境をつくり、よりスピーディーに開発できる環境を構築したいと考えています。

黒木
私も大坪さんと同様、業務効率化に関心があります。特に私の場合はフロントエンドの領域に興味があるので、デザインカタログ作りなどをやっていきたいと考えています。

大坪
やりたいことは手を挙げればどんどん任せてもらえます。
例えばエンジニアのスキル可視化ツールです。スキル伸長を継続的に見るためには「定量的な指標が必要なのでは?」と課題意識を持ち、企画を開始しました。結果的にSBUデジタル開発室に留まらず、本部全体でスキル可視化が必要だということで、個人の企画が本部企画まで昇華されることとなり、非常に貴重な経験ができたと感じています。CoEプロジェクトをまたいだコミュニケーションが盛んだからこそ、このような横展開が実現していくんだなと感じました。

佐藤
コミュニケーションをとる頻度は非常に多いですね。個別の1on1だけではなく、室全体やCoE全体でのミーティングも定期的に実施していることから、SBUデジタル開発室に留まらないコミュニケーションがあると感じます。

黒木
起業を経験した際はメンバーが限られていたため、密にコミュニケーションを取っている感覚がありました。しかし、人数が格段に多い現在も、良いコミュニケーションを取れていると感じますね。
また、チーム内でエンゲージメントに関するアンケートを取ったところ、「自己成長」「チームワーク」「役割認識」の数値が特に高かったんです。全員が同じ方向を向きながら、それぞれの自己実現のためにやるべきことに取り組めているからこそ、このようにチームワークを発揮できている感覚があるのだと感じています。


佐藤
パーソルホールディングスのエンジニア組織は裁量権を持ってはたらけるのが魅力です。先ほどお話しした大坪さんの企画しかり、良い提案はどんどん採用し、開発できるのが特徴ですね。コミュニケーションの総量が多いので、自分の意見やアイデアも反映されやすいです。
また、フルスタッフエンジニアを目指すため、一つの領域に留まらず新しい領域にどんどん挑戦できます。そのため、自律的に組織に貢献していきたいという方にとっては魅力的な環境ではないでしょうか。

大坪
コードを書き、求められる要望に応えるだけでなく、開発組織の環境や仕組みを作る経験ができるのがパーソルホールディングスの強みです。言われたことを淡々とこなすのではなく、明確にやりたいことがあったり、それを実現したりしたい方にはうってつけの環境だと思います。
特に組織作りに興味がある方との親和性は高いですね。私自身も組織として勉強する風土を作っていきたいと考え、最近は輪読会や勉強会などを主催しています。このように、ものづくりに留まらない経験をしたい方にはとてもおすすめです。

黒木
まだ組織ができたばかりなので手探りな部分が多いですが、自分たちのアイデアが形になったときの達成感が非常に大きいです。また、私自身「チームで何かを成し遂げたい」と思いパーソルホールディングスに入社しましたが、今まさにそれを体感できています。一人ではなし得ないような大きなことに挑戦したい方に、ぜひお越しいただきたいですね。
取材・文=佐原有紀(ファーストブリッジ)
※所属組織および取材内容は2024年6月時点の情報です。
※略歴内の情報は2025年10月時点での内容です。
1

STRATEGY
【後編】未来の“はたらく”を変革する——パーソルホールディングス×パーソルクロステクノロジー 両本部長が語る、AI戦略と共創の最前線
2

PROJECT
わずか10カ月で開発・導入を実現。データドリブンなタレントマネジメント基盤を形にした舞台裏
3

PROJECT
課題の本質をとらえ、伴走型の支援を―コンサルティング×テクノロジーで拓く、地域共創の最前線
4

PROJECT
生成AIによって「女性のはたらき方」が変わり始めた―クラフター小島氏×パーソルテンプスタッフ朝比奈対談
5
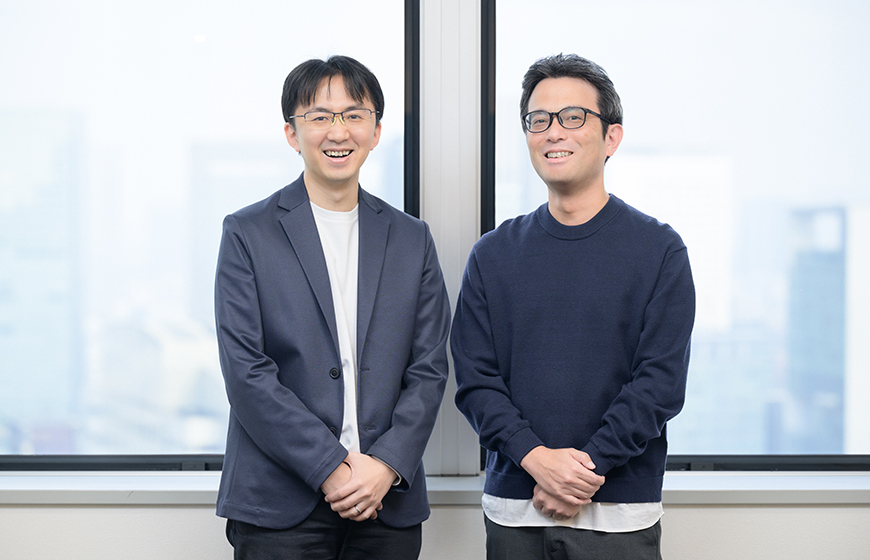
PROJECT
30を超える基幹システムを“無風”でクラウドに。パーソルテンプスタッフが挑むアプリリフト