STRATEGY
“自分らしくはたらける”を支えるインフラの仕組みづくり。グループIT本部の現在地

パーソルホールディングス株式会社
グループIT本部 ワークスタイルインフラ部
コミュニケーションインフラ室
プロダクトオーナー/リードコンサルタント
2020年、パーソルホールディングスへ新卒入社。新規Microsoft サービスの社内展開やTeamsの機能拡張、Power Platformの利活用推進を行っている。
パーソルホールディングス株式会社
グループIT本部 ワークスタイルインフラ部
コミュニケーションインフラ室
コンサルタント
2016年4月、パーソルテンプスタッフへ新卒入社。人材派遣事業の新規・既存の営業活動を担当。派遣スタッフの雇用の場を作る中で「はたらく仕組み」の重要性を感じ、2023年1月にパーソルホールディングスへ転籍。現在は、社員のコラボレーション強化や生産性向上を目指し、Microsft365サービスを中心としたツールの機能拡張や導入に従事。
2023年9月、パーソルホールディングスは、業務効率化を目的に、Microsoft が提供するチャットベースの生成AIインタラクション「Microsoft 365 Copilot」の利用促進を目的としたプロジェクトを発足させました。効果検証から全社展開に至るまでの全プロセスの中心を担ったのは、コミュニケーションインフラ室 Modern Communicationチームの西山と荒木です。
ふたりは、Microsoft 365 Copilotという新たなツールを社員にどのように浸透させていったのでしょうか。推進の裏側と導入の手応え、さらに今後の展望について聞きました。

西山
プロジェクトの実務面を取り仕切ってくれた荒木と連携しながら、プロジェクトの方針や企画内容の精査、また、施策の円滑な実施をサポートしつつ、プロジェクトオーナーとして、関係各所との調整や意思決定を担いました。

荒木
私は主にMicrosoft 365 Copilotの利活用を推進するための施策の立案と実行を担当しました。プロジェクトには、私と西山に加え、2名の上長と技術的サポートを担っていただいた3名の外部パートナーを含む総勢7名が関わっています。

西山
コミュニケーションインフラ室は「Microsoft Teams」や「Microsoft Outlook」などのMicrosoft製品や、ファイル共有サービスの「Box」など、グループ各社の従業員が業務で利用する各種コミュニケーションサービスの社内導入を管轄する組織です。
なかでも、私たちModern Communicationチームは、とくに使い方に工夫が必要で、業務改善や効率化に直接つながるサービスを管理しており、その関係で今回のMicrosoft 365 Copilot利活用推進プロジェクトも担当することになりました。そのほか、チームとしてはAI搭載のローコード開発ツール・Microsoft Power Platformや社内版SNSであるMicrosoft Viva EngageなどのMicrosoft 365製品の導入や運用、新機能の展開を行っています。

西山
パーソルグループは、「パーソルグループ中期経営計画2026」に掲げている通り「テクノロジードリブンの人材サービス企業」を目指しており、2023年から本格的に生成AIの業務活用に乗り出しています。Microsoft 365 Copilot利活用推進プロジェクトもその取り組みの一環としてはじまったもので、2023年9月の活動開始後、Phase1、Phase2と段階を踏み、2025年5月にグループ全社に正式展開されました。


西山
パーソルグループは、以前からMicrosoft製品を多数利用していた関係で、日本マイクロソフト社から一般公開に先駆け、Microsoft 365 Copilotの先行プログラムへの参加を打診いただいたのがはじまりです。
先ほども少し触れたように、経営陣も生成AIの活用には非常に前向きではあるものの、ITを得意とする部署ばかりではありません。黎明期の生成AIであればなおさらです。どうやって使うべきかわからない状態のまま「使ってください」といっても、活用が進まないのは明らかでしたから、Microsoft 365 Copilotの利活用を後押しし、業務効率化につながるのかを検証するこの取り組みをはじめることにしました。

荒木
プロジェクトがスタートした2023年9月から翌年8月にかけて実施したPhase1では、比較的ITに詳しいユーザー300名にライセンスを配布し、効果検証を行いました。その結果、非常に良好な数値が得られたため、2024年10月からはより効果的な活用方法を探るべくPhase2に移行し、ユーザー数を750名まで拡大しました。
ここでさらなる効果が確認できたことから、2025年5月にはグループ全社へ展開し、希望ユーザーはライセンスを購入して業務活用できるようになりました。

荒木
Phase1のスタートから11カ月経過した2024年8月に実施した第1回効果測定では、1日あたりの業務時間が1人あたり月平均で2.6時間削減され、MAU(月間アクティブユーザー数)は80.9%、ROI(投資収益率)は199%と、良好な結果を残すことができました。
2024年12月実施の第2回効果測定では、削減時間はさらに3.6時間に伸び、MAUは97.3%まで上昇。ROIについては269%と圧倒的な成果が出たため、2025年5月以降は、国内38社のIT予算を使って必要なライセンスが購入できる環境をつくりました。

荒木
まずは私たちが、日本マイクロソフト社が主催する交流イベントに参加し、先行する他社の事例を吸収し、人脈を築くことからはじめました。他社のみなさんと意見交換したり、コラボイベントを実施するなかで得たノウハウを貯める一方、Microsoft 365 Copilotの有効な利活用を共有する目的とした社内コミュニティの開設と運営、定期的なオンラインライブイベント実施、投稿数に応じたポイントを付与や知見共有のためのアプリの配布、さらには、ユーザー座談会や階層別、職種別トレーニングなどにも取り組みました。

荒木
社内にはさまざまな業務に取り組む社員がおり、生成AIに対する認識や関心にも幅があります。そうした多様な方々に「自分も使ってみたい」と思ってもらえるよう、継続的に魅力を伝えていくのはとても重要です。とはいえ、パーソルグループには約5万人の社員がおり、私たちだけですべてのニーズに応えることはできません。
そこで、私たちよりも先行して活動をはじめていた社内のAI推進グループ「CHASSUUコミュニティ」の参加者にMicrosoft 365 Copilotを試してもらったところ、現場ならではの活用事例やノウハウを多数共有していただけました。こうした地道な取り組みが、多くの社員の意欲を引き出し、その結果が効果測定の数値にも表れたのだと思います。

西山
コミュニティ運営やオンラインイベントを主催した経験がなかったのですが、他社のみなさんからの支援や協力もあって、オンラインライブイベントには毎回100名ほどの視聴者を集めることができました。これまで経験のなかった施策に取り組むうえでは、社内外を問わず広く知見や情報を持つ方々とつながりを築くことが大事なんだと改めて実感しています。

荒木
なるべく多くの方々に親しみを感じてもらえるよう、機能紹介だけで終わらせず、キャッチーなタイトルや可愛らしいデザインにこだわって、楽しんでもらうことを重視したコンテンツづくりに努めたのもよかったかも知れません。


西山
議事録やメールの作成や要約、外部向けの文書作成やプレゼン資料、企画書の執筆補助、データの集計、分析など、業務効率化が中心です。当初は「どんなプロンプトを書けばいいかわからない」という悩みを耳にする機会が多かったのですが、あるユーザーが「それをMicrosoft 365 Copilotに直接聞いてみれば?」と話しているのを聞いて、目から鱗が落ちるようでした。
ITリテラシーに長けている方だけでなく、コミュニケーションスキルが高い方はAIとうまく対話をして使いこなしているのは、ほかのITサービスとの大きな違いといえそうです。

荒木
私はMicrosoft 365 Copilotの新機能を紹介する広報記事を書く際に必要な情報を集めたり、文面の素案づくりに利用したりすることが多いですね。このほかにも何百人分のアンケートの集計や分析などにも使っており、さまざまな業務に対応可能な頼れるアシスタントのような存在です。

西山
私は立場上、各方面から集まってくる情報をキャッチアップしなければならないため、メールや議事録、そのほかのドキュメントを要約してもらったり、情報収集や資料作成などに利用したりしています。Microsoft 365 Copilotはもはや日常業務に欠かせないツールです。

西山
私たちを含め、主に文章の生成や要約など汎用的な業務の効率化が中心ですが、いずれは生成AIエージェントの活用を前提に、事業変革につながる活用に展開していかなければなりません。Microsoft 365 Copilot活用の裾野を広げる一方、利用の高度化に取り組んでいかなければと考えています。

荒木
社員全員が手軽に使えるCHASSUと、専門的かつ高度な利用ができるMicrosoft 365 Copilotを使い分けながら活用事例を増やし、だれでもAIエージェントを活用した市民開発が当たり前に行えるような環境づくりや支援策を展開するが今後の課題です。

西山
業務担当者自身が業務特化型AIエージェント使いこなせるようになれば、その効果は計り知れません。

荒木
そうですね。Microsoft 365 Copilotに限らず生成AIは日々、目覚ましい進歩を遂げており、私たち自身がノウハウの蓄積や伝え方をアップデートしていく必要があります。そう考えると、むしろこれからが本番です。引き続き気を引き締めてMicrosoft 365 Copilot活用を推進していきたいと思っています。

取材・文=グレタケ 武田敏則
※所属組織および取材内容は2025年8月時点の情報です。
※略歴内の情報は2025年10月時点での内容です。
1

STRATEGY
【後編】未来の“はたらく”を変革する——パーソルホールディングス×パーソルクロステクノロジー 両本部長が語る、AI戦略と共創の最前線
2

PROJECT
わずか10カ月で開発・導入を実現。データドリブンなタレントマネジメント基盤を形にした舞台裏
3

PROJECT
課題の本質をとらえ、伴走型の支援を―コンサルティング×テクノロジーで拓く、地域共創の最前線
4

PROJECT
生成AIによって「女性のはたらき方」が変わり始めた―クラフター小島氏×パーソルテンプスタッフ朝比奈対談
5
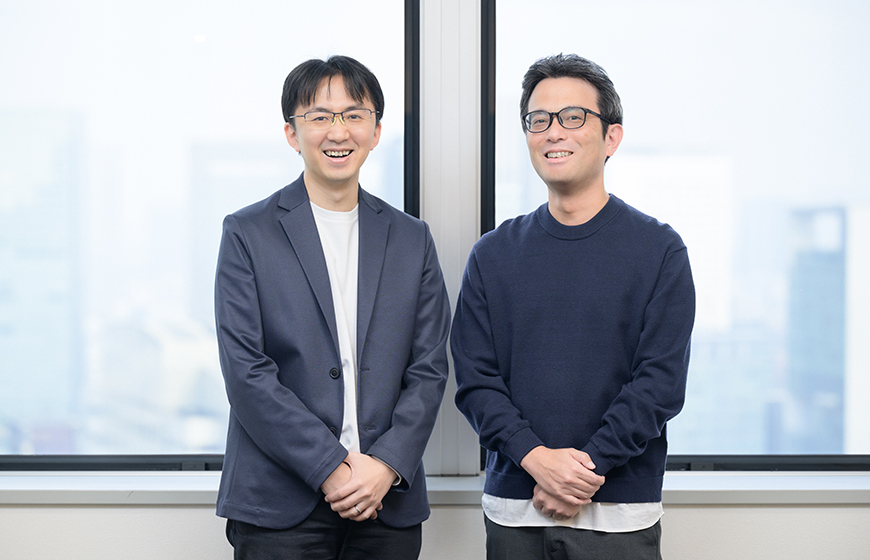
PROJECT
30を超える基幹システムを“無風”でクラウドに。パーソルテンプスタッフが挑むアプリリフト