REPORT
第8回パーソルグループ テクノロジーLONG Meeting開催

パーソルテンプスタッフ株式会社
執行役員 CIO
外資系プロジェクトマネジメントソリューションベンダーにてプロダクト開発、導入を中心に担当。外資系ITセキュリティ会社2社でコーポレートIT部門のリーダーシップを執った後、2014年にパーソルキャリア(旧インテリジェンス)に入社。2021年よりパーソルホールディングス グループデジタル変革推進本部 本部長としてグループ全体のデジタル変革を推進。2025年より現職。
2024年度(第42回)IT賞(マネジメント領域)受賞、第9回HRテクノロジー大賞人的資本経営部門優秀賞、JAPAN HR DX AWARDS 2024特別賞 受賞。
パーソルホールディングス株式会社
グループIT本部 ワークスタイルインフラ部
デジタルEX推進室
室長
移動体通事業の店舗運営/営業7年、ITインフラエンジニア5年、ITサービスマネジメント領域のコンサルティング、セミナー講師3年などの経験を経て、パーソルホールディングスへ入社。入社後は、PC、拠点ネットワーク、TV・Web会議、電話等のサービスマネージャ業務に従事したのち、アジャイルパイロットチームとしてKRaFTサービスの企画、開発チームを立ち上げ。2023年10月にデジタルEX推進室に着任。
2024年11月26日(火)、パーソルホールディングスが主催する勉強会「社内生成AI活用を推進するために、知っておくべき開発戦略と文化醸成──パーソルホールディングス導入事例を紹介」に、パーソルホールディングス 朝比奈ゆり子、上田大樹が登壇しました。
生成AIを導入したものの、「ガバナンスやルールの整備が不十分でうまく使えない」「拡充のための予算やリソースの確保ができない」「社員が生成AIを活用しきれない」といった問題に直面している企業や担当者の方々へ向け、30社以上の国内グループ会社において生成AIの活用を推進したパーソルホールディングスの取り組み事例を紹介しました。
今回は、当日お話しした内容から一部抜粋・編集の上でご紹介します。
最初に登壇したのは、パーソルグループのDX推進の旗振り役である朝比奈だ。朝比奈は、DX推進の要素の一つとして欠かせないことから、生成AIの推進を担当している。「今回は、包み隠さずリアルにお話させていただきます」と述べた。
パーソルホールディングスは、2024年11月13日に生成AIの業務利用に関するニュースリリースを配信した。「パーソルの国内グループ社員の1万8,000人以上が生成AIを利用事業活用、業務利用を積極推進している」というリリースだ。

パーソル、国内グループ社員の1万8,000人以上が生成AIを利用事業活用、業務利用を積極推進 | パーソルホールディングス株式会社のプレスリリース
パーソルホールディングス株式会社のプレスリリース(2024年11月13日 11時21分)パーソル、国内グループ社員の1万8,000人以上が生成AIを利用事業活用、業務利用を積極推進
同社の社員数は約1万8,000人以上。
朝比奈:私たちのオフィスで主に勤務している社員のほとんどが、生成AIを活用しています
パーソルグループのテクノロジー戦略は次の四象限で表すことができる。生成AIに関してもすべての領域に当てはまると考えた。
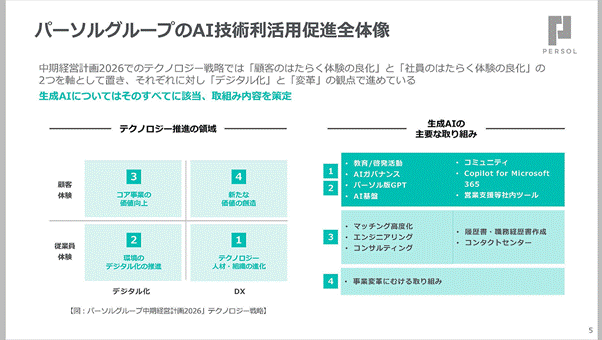
1つ目と2つ目は従業員体験共通の領域、3つ目と4つ目の取り組みは事業そのものに生成AIを取り入れていくための取り組みだ。今回のセッションで紹介したのは、従業員体験の共通領域の教育/啓発活動、AIガバナンス、パーソルグループ版GPT、AI基盤などの整備などである。
パーソルグループの生成AI導入の旅が始まったのは2023年4月だ。導入を進めるためまず、法務を含めた複数部門からなる推進チームを結成した。「パーソルグループ社内版のGPTを、絶対に作らないといけないと思ったためです」と朝比奈は語る。
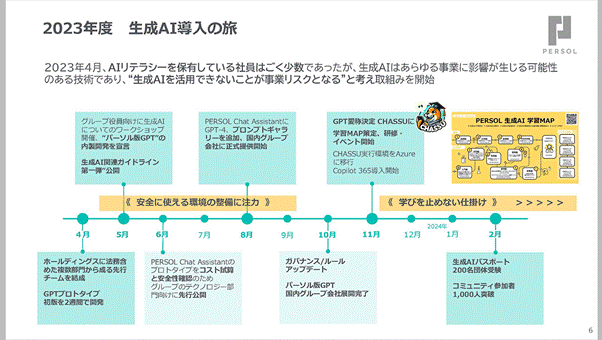
プロトタイプ初版は2週間で開発できた。「これならいける」と思った朝比奈は、5月にはグループ役員向けに生成AIについてのワークショップを開催し、パーソル社内版GPT(以下、社内版GPT)の内製開発を宣言した。
朝比奈:そこから9月末までは、国内のグループ会社に展開するため、安全に使える環境を作っていくことに注力しました
国内グループ会社への展開が終わった後は、社内版GPTを使い続けていくための仕掛け、学びを止めないための仕掛けを整備していった。
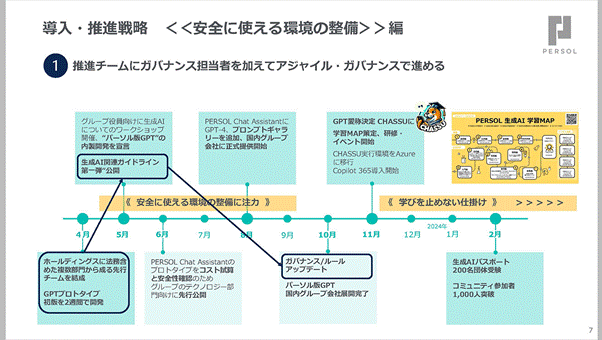
この一連の流れで、朝比奈は生成AIの業務利活用に結び付けた。ガバナンスの整備をするための第1のポイントが、「推進チームにガバナンス担当者を加えてアジャイル・ガバナンスで進めたこと」だった。
AI特有のレビューのポイント、審議者を加えた審議プロセスを構築することも意識した。さらにレビューには法務、情報セキュリティ担当者に加え、データやAI技術を理解しているメンバーも含め、一緒にルールを作っていった。
朝比奈:一般社員が参照するAIサービス利用における汎用的なセキュリティガイドラインの第一版は4月に公開しました
以降は必要に応じて、ガイドラインをブラッシュアップ、9月にはアップデート版を公開している。また、企画者・審議者向けのガイドラインやチェックリスト形式のリスクアセスメントツールも作成。これも適宜、アップデートしているという。
第2のポイントは経営層の理解を促すことだ。そのため、経営層に話すタイミングを計っていた。
タイミングとなったのは、5月に実施されたグループの役員が集まるオフサイトミーティングの場。ワークショップを開催し、外部コンサルタントから世の中の変化予測を伝え、生成AIの取り組みの必要性をインプットした。
すると、ミーティングの場で取り組まないといけないという雰囲気となったため、「パーソルでは、すでに社内版GPTの開発に取り組んでいるので任せてください」と宣言。社内版GPTを作る許可を取った。その後、経営層へのインプットは投資とリターンをセットで説明を行った。だが、取り組み始めた頃は、API利用料も確定していなかったため、正式なコスト見立てが困難であった。
そのため、月額100万円を上限とし、その範囲内でリテラシーの高いIT系の部門とコンプライアンス関連の部門に使ってもらうことにした。「最初から定量目標を定めることは難しいので、導入後に算出するというアプローチもあると思います」と朝比奈はアドバイスする。
また、KPIも利用が進むにつれて変化させたという。最初のKPIは利用者数だったが、後に効果発出時間へと変えたのだ。
朝比奈:経営会議では取り組み状況と共に、KPIについても報告しています。真に目指すべきは業務改革なので、今のKPIは投資だと思ってみてくださいと、丁寧に説明しています
オフィシャルな場だけのインプットでは難しいと思い、自身で経営層向けにメルマガも発信。こうして経営層をスポンサーにつけることを行ったという。
朝比奈:最初は2週間に1回、今は1カ月に1回の頻度で経営層に絞ってメルマガを送信しています
こうして環境を整え、続けていったのが利用する社員が学びを止めない仕掛けづくりである。まず、生成AIを活用するための仕掛けを考えた。生成AIの学びの体系をどう整えれば良いのか。そんなときに参考になったのが、経済産業省の「生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方」だった。それを参考に学習体系をまとめた。
朝比奈:このまま発信しても面白くないので、一般社員向けには生成AI学習マップという形にまとめて、ビジュアルも含め、楽しい打ち出しにして展開しています
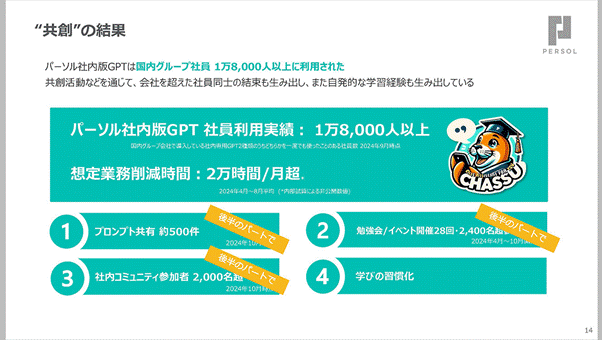
社内版GPTを最初にリリースしたときの利用率は、約10%だった。だが、ふたを開けてみると国内グループ社員1万8,000人以上に利用されるという結果になった。(2024年11月時点)
生成AIを利用することで業務工数削減をはじめ、いろいろな効果が得られているが、朝比奈が取り上げたのが、「社員の学びの習慣化」だ。2024年2月、生成AI活用普及協会の「生成AIパスポート試験」にトライすることを社内コミュニティに問いかけたところ、社員200人が受験に参加したという。
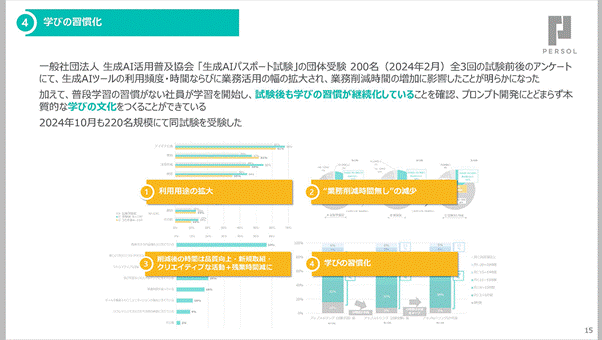
試験前後の社員アンケートでは、生成AIツールの利用頻度や時間、業務活用の幅が拡大され、業務時間の削減の増加に影響したことが明らかになった。特に嬉しかったのは、「学びの習慣が継続したこと」と話す。しかも学びが生成AIに閉じていないというのだ。
朝比奈:今後はお客さまに提供するサービスにも生成AIを活用できるよう、体制を整えていきたいと考えています
続いては、2023年10月に発足したデジタルEX推進室室長を務める上田が登壇した。
上田は営業出身で、その後ITエンジニアに転身。SIerでインフラエンジニアとして経験を積み、コンサルティングやセミナー講師などを経て、現職に。今もエンジニアとして活動しつつ、デジタルEX推進室の室長として、生成AI利活用の促進に取り組んでいる。
上田:今回は取り組みを振り返り、本当に良かったと思えるポイントを中心に紹介します
一つは発足の段階でモチベーションが高まっていたことだという。パーソルグループの生成AIの推進体制は、誰かの一声でできたものではない。「ボトム、ミドル、経営層それぞれの活動が結果としてつながって体制が作られた」と話す。
パーソルでは、「2030年に向けた価値創造」のストーリーが全社員に浸透。このストーリーの中ではテクノロジードリブンの人材サービス企業を経営の方向性として、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」を目指していくことを掲げている。
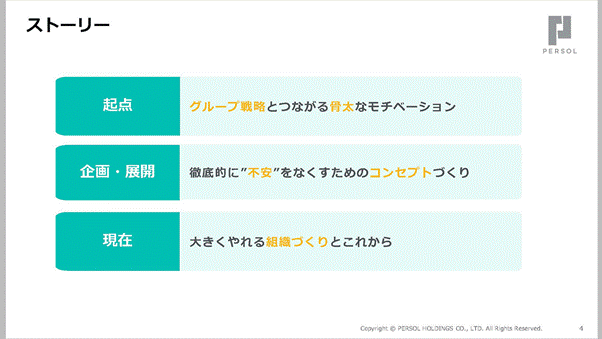
上田:社員は常に、どうやってテクノロジーの力で“はたらくWell-being”を実現していくのか、考えながら仕事をしています。そういう環境の中で、生成AIという技術に可能性を感じた私ともう一人のエンジニアがプロトタイプの開発や生成AIを使える環境作りをしていきたいとボトムアップで上司を説得しました
それと同じタイミングで、ミドル層では朝比奈を中心に経営層を説得。このようにして推進チームが構成されたのだ。
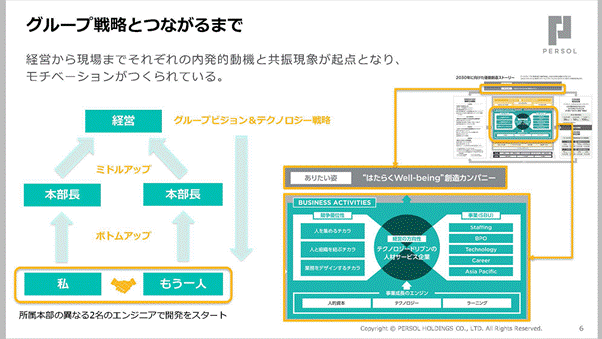
だが、生成AIについて社員の意見を聞くと、個人として利用する分には「ワクワクする」「期待している」などポジティブな意見が聞かれたが、業務で活用するとなると、「大半のコメントがネガティブなものだった。不安感が顕在化していた」と上田は明かす。
一口に不安と言っても担っている役割の違いによって異なる。例えばガバナンス担当者の場合、どこまで制限して、どこまで許可するのか、何をベースに検討して、どのように統制すれば良いかなどのコメントが見られた。
業務で利用したいと考えている社員のコメントでは、各自の業務で活用して良いのか。また、その注意点は誰に相談すれば良いのかなど、ルールが公開されていないために誰に相談しても答えが見つからないなどといった声もあった。
上田:世の中では生成AI活用が進んでいるのに、業務で利用できないのは市場価値に差が生まれるのではという危機感を持つコメントもありました
経営層の場合は、既存マーケットの変化や破壊、またそれらの変化にどう対応するのか。生成AIを活用した場合のリスク、活用しなかった場合のリスクはという不安が挙がっていた。
これらの不安を解決するために、「安心安全、学び・共創、育成という3つのコンセプト」を作った。コンセプトを掲げたことで、組織力が向上し、ぶれない戦略を打てたのだ。
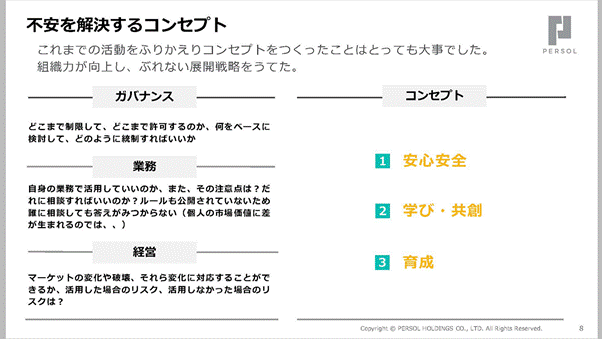
この3つのコンセプトに従い、生成AI推進チームが発足した。安心安全というコンセプトでは、社内標準コラボレーションツールであるMicrosoft Teams版を用意した。
上田:一目で社内ツールとわかる仕様とし、Microsoft Azure環境も合わせて整備し、企業内のクローズドな環境で構築しました
また、生成AIガイドラインも整備した。「一般サービス利用者向け」と「プロダクト・企画・開発・審査部門向け」に体系整理したほか、リスクアセスメントツールを作成し、グループ会社に展開した。さらに特徴的なのが、リスク相談窓口を開設したことだ。
上田:IT、法務、情報セキュリティのメンバーが常駐するようにしました
学び・共創というコンセプトでは、プロンプトを他の社員に共有するための仕組み「プロンプトギャラリー機能」を搭載した。「すでに500件以上のプロンプトが溜まっています」と説明する。
さらにこうしたツールの提供だけではなく、社員が「生成AIマスター」になるための道のりを描く学習マップを作成し、それを軸に社内イベントや研修を実施した。リアルタイムで参加できなかった社員は、プレイリストという形でアーカイブ視聴できるようにしている。
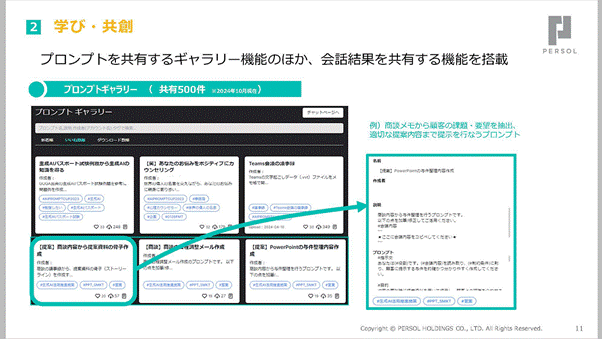
育成というコンセプトでは、生成AIに親近感をわかせるため、CHASSUというキャラクターを作成。その上で社内コミュニティ運営を行っている。
上田:コミュニティでは社員の声を拾い上げる仕組みで、社員が開発に参加している体験を創出することで、内製開発による高速なエンハンスにつなげています
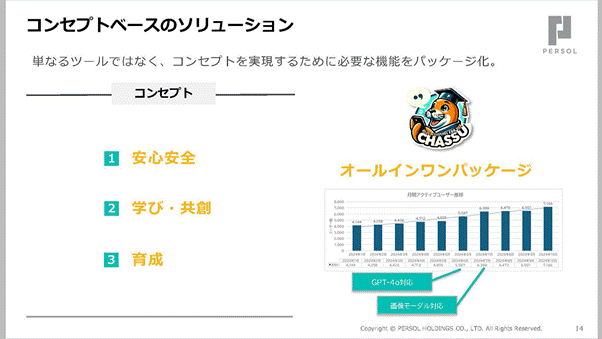
当初十数人から始まったコミュニティだが、今では2,000人もの社員が参加している。
このようにパーソルグループが1年強で、生成AIの業務への利活用を進められたのは、単なるツールとしてだけではなく、安心安全、学び・共創、育成という3つのコンセプトを実現するために必要な機能をパッケージ化して社内に展開したからだと言えるだろう。
開発エンジニア2人からスタートし、法務のメンバーなども加わったものの少人数で進めてきた生成AI推進チームだが、今、注力しているのがCHASSUのメジャーアップデートだ。
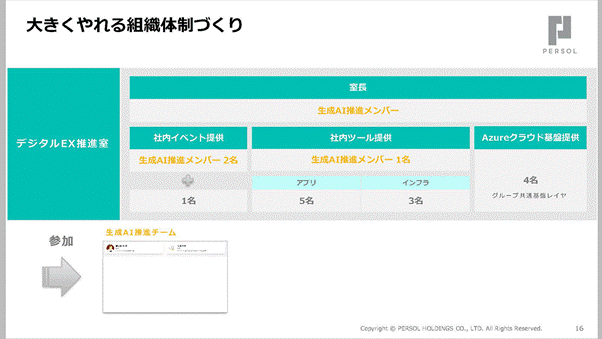
今後を見据え、音声入力やWeb検索機能などの機能拡張・改善を図っている。
上田:現在は私たちのミッションに共感いただける方を外部から積極的に採用し、デジタルEX推進室を、さらに大きくできる組織作りに取り組んでいます
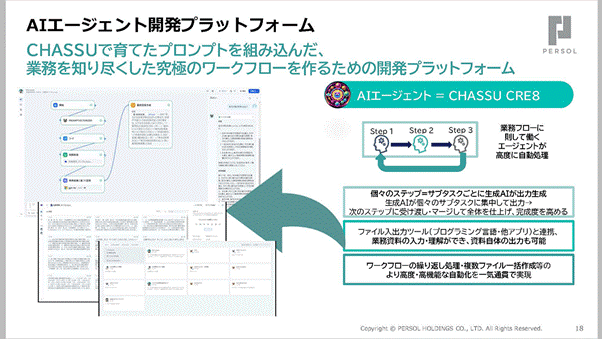
さらに現在は、生成AIのエージェントをノーコードで開発できるプラットフォーム構築にも取り組んでいる。
セッション後のQ&Aタイムでは、参加者から非常に多くの質問が寄せられた。その一部を紹介する。
Q.
法務を仲間に加えるために必要な交渉事はどのようなものだったか?

朝比奈
法務トップを捕まえて、生成AI技術について簡単に説明し、協力を依頼したところ、一発OKをいただきました。
というのも法務の中でもAIについてプロファイリングや、プライバシーに関して調べるなどの取り組みをしていました。そこに技術がわかる人が入ってくれるのならと、法務としても諸手を挙げて賛成してくれたという状況でした。
Q.
生成AIの社内導入推進は、ともすればトラブルがあったときに責任をなすりつけられたりしないのか、朝比奈さんの心構えが聞きたい

朝比奈
この推進を実践するのは自分しかいないなと思ったのです。もちろん、「セキュリティ>コスト」の順で考え、大きなトラブルにならないようにマネジメントすることは前提となります。しかし、ガバナンスも環境も、事業適用も、キャラクター的にも押せるのは私しかいないと思いました。
Q.
100万円という予算は何か根拠があったのか?

朝比奈
根拠はありません。エイヤという気でいきました(笑)。最初の数か月の支払は20~30万円台/月だったと記憶しています。

上田
最初、どのくらいかと聞かれたのですが、答えようがありませんでした。すると、とりあえず100万でいくかと言われ、それでいきましょうと答えました。
Q.
コミュニティのオーナーなどは立てたのか、Webサイトは独自に作ったのかなど、運営の詳細が聞きたい

上田
コミュニティをどこに作るのか、正解はまだ出ていません。当社ではMicrosoft Teamsがコミュニケーションツールとして社員全員に浸透しているので、Teams内にコミュニティを作り、生成AI推進チームがオーナーとなってコミュニティを盛り上げています。もちろん、社員はそこに自由にアクセスできます。
コミュニティの形成方法には、強制的にメンバーを招集する方法と自由参加型のものがありますが、我々が選んだのは自由参加型。こちらの方が自発的に入ってくる社員が増えると考えたからです。
当初はオーナー側で発信することがほとんどでしたが、最近はコミュニティに参加している方の発信の方が多いので、この方法を選んで良かったと思っています。
Q.
プロンプトギャラリーをどうやって作ったのか

上田
AIチャットツールそのものは、Next.jsで開発したスクラッチのWebシステムです。プロンプトギャラリーはその一機能として開発しました。
プロンプトギャラリーを盛り上げるためにオーナー側が意識していることの一つを挙げるとすると、「おもしろいで賞」「業務に活用できるで賞」などの賞を用意し、毎月、社員を表彰しています。
Q.
Copilot・ChatGPTなどの生成AIと社内AIの棲み分けや使用方法の違いは、明確にして社員の方への活用を推進したのか?

上田
明確な棲み分けはしていません。他のAIツールも含めて整理をしていかないといけないと思っています。
Q.
RAGへの取り組み状況はどうか、ニーズはあるか、実装は進んでいるかなどを聞きたい

上田
ニーズは根強く、CHASSUという汎用ツールとしては継続的に検討をしている大きなテーマです。グループ内の様々なプロダクトでRAGへの取り組みが始まっており、精度向上をさせるための手法を検討したり、社内データを検索インデックス化する取り組みをしてみたりという状況です。
イベント開催時間中には回答しきれないほどの質問が寄せられ、非常に盛り上がったイベントとなった。
パーソルホールディングス、そしてパーソルグループでは今後も、グループ社員の従業員体験の向上をはじめ、事業への生成AI活用にも積極的に取り組んでいく。
(※2025年1月時点の情報です。 )
1

STRATEGY
【前編】生成AIで変革を加速せよ——パーソル各社の事業をアップデートするグループAI・DX本部の挑戦
2

PERSON
パーソルグループがビジネスモデル変革を視野に狙う、AI活用の未来予想図
3

PERSON
データとAIに注力する新組織で、パーソルグループはどう変わるのか? データサイエンス室長が見据える未来
4

PROJECT
テクノロジーだけでは変われない、「企業風土の変革」こそ本質的なDX推進のカギークールスプリングス三枝氏×パーソルテンプスタッフ朝比奈対談
5

PROJECT
社内イベント「AI Summer Fes」開催!生成AIで業務効率化や新しいはたらき方にチャレンジ