STRATEGY
「守り」だけでなく、DXを具体化する「攻め」も両立できるIT組織を目指して――パーソルテンプスタッフ「テクノロジー本部」が掲げるミッションと戦略

クールスプリングス株式会社
Founder & CEO
国立東京工業高等専門学校卒業後、ブリヂストン入社。2013年に工場設計本部長となり生産拠点のグローバル展開を推進。2016年に生産技術担当の執行役員に就任。2017年よりCDO・デジタルソリューション本部長。2020年に出光興産へ執行役員CDOとして移籍、2021年に執行役員CDO/CIO兼デジタル・DTK推進部長、同2021年「Japan CDO of the Year」を受賞。2014年には、会社勤めと並行してクールスプリングス株式会社を創業。DX支援事業、賃貸不動産、飲食店等を営む。
パーソルテンプスタッフ株式会社
執行役員 CIO
外資系プロジェクトマネジメントソリューションベンダーにてプロダクト開発、導入を中心に担当。外資系ITセキュリティ会社2社でコーポレートIT部門のリーダーシップを執った後、2014年にパーソルキャリア(旧インテリジェンス)に入社。2021年よりパーソルホールディングス グループデジタル変革推進本部 本部長としてグループ全体のデジタル変革を推進。2025年より現職。
2024年度(第42回)IT賞(マネジメント領域)受賞、第9回HRテクノロジー大賞人的資本経営部門優秀賞、JAPAN HR DX AWARDS 2024特別賞 受賞。
パーソルグループでは、「テクノロジードリブンな人材サービス企業」という経営の方向性を掲げ、DX推進を加速させています。しかし、DXをただ推進するだけで変革を起こすのは容易ではなく、組織の風土改革も同時に進めることが不可欠です。
そこで今回は、数多くの企業でDX推進と組織変革を同時に進めてきたクールスプリングス株式会社 代表取締役 三枝幸夫氏をお招きし、パーソルテンプスタッフ株式会社 執行役員 CIOの朝比奈が話を伺いました。
企業風土改革を伴うDX推進の要諦や、経営層から現場に至るまで全員を巻き込むための具体的な仕組みづくりを、じっくりと探っていきます。

朝比奈
三枝さん、本日はよろしくお願いします。私自身、パーソルグループでDX推進を担う立場として、「どうやったら本当の変革が起こるのか」をもっと学びたいと思っています。まずは、これまでのご経験を改めて伺えますか?
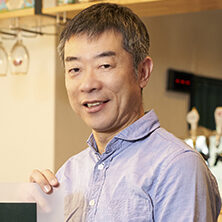
三枝
私は新卒でブリヂストンに入社し、ファクトリーオートメーションやプロセス制御などを中心に、モノづくり領域に30年以上携わってきました。その後、リーマン・ショックを機に「製造業はモノづくりだけでは生き残れない」という経営判断のもと、CDO(最高デジタル責任者)として、データ活用を軸とした新たなサービスの仕組みづくりを推進していったんです。
そこから2020年には出光興産へ移り、脱炭素時代に対応するため、ガソリンスタンドを地域の多様なサービス拠点へと進化させる取り組みに注力しました。しかし、組織全体を変えるには想像以上の時間を要し、1社ずつ対応することへの時間や範囲に限界を感じたんです。そこで、より広くDXを日本に普及させたいという思いから、2024年3月に出光興産を退社し、今は自社でデジタル化の教育や支援サービスを多くの企業へ提供しています。

朝比奈
ありがとうございます。私もグループ全体でDXを進める中、テクノロジーを導入してもなかなか変わらない部分が多いと感じています。そこで、「企業風土の改革」が重要になると思いますが、三枝さんはどのように捉えていますか?
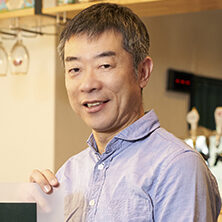
三枝
まずは、「会社として何を実現したいのか」を明確にすることが大切ですね。少子高齢化による人材不足といった環境変化の中で、事業を発展させるためにテクノロジーをどう活用していくかを考える必要があります。

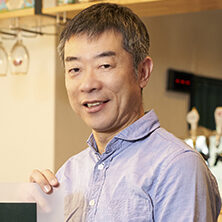
三枝
ただ、いくらテクノロジーを導入しても、実際に業務を担当する人たちが「なくても仕事は回る」と感じれば活用されません。だからこそ、新しい技術を積極的に取り入れられる文化――つまり風土改革が不可欠だと考えています。

朝比奈
たしかに。パーソルグループでも、現行の中期経営計画に「テクノロジードリブンの人材サービス企業」を掲げたことで、生産性を高め、より質の高いサービスを提供していく意識が組織全体に浸透しつつあります。やはり文化醸成につながる風土改革は必須ですよね。

朝比奈
「経営層が方針を示すだけでは不十分」という点は共通認識かと思います。では、現場が主体的に新しい技術を取り入れていくには、具体的にどのような工夫が必要でしょうか?
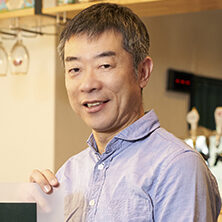
三枝
最も重要なのは、一人ひとりが主体的に考える環境を整えることです。組織としてのビジョンを明文化し、部署やチームの行動計画に落とし込むことで、「自分ごと」として捉えやすくなります。実際に私が推進してきた施策でも、どのように改善すれば成果に結びつくかを明確にし、共有する仕組みづくりに力を注いできました。
特に、効果が実感しやすい生成AIを導入する場合は、具体的な活用シーンを座学や研修などで理解してもらうだけでも効果が大きく変わります。加えて、他企業での成功事例を参考にしながら、自社の業務に応用すれば、現場への浸透はさらに加速するでしょう。

朝比奈
ビジョンの浸透ですね。実はパーソルでも、生成AI活用のコミュニティをつくり、グループ内に展開したところ、各所から「こんな効果が得られた」「こういう事例をつくりたい」といった報告が自発的に寄せられました。表彰制度を導入するなどの工夫を凝らすとさらに活気づき、「これこそがカルチャーを変える力なんだ」と強く感じました。
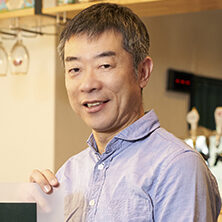
三枝
私も新たな取り組みを推進する際、“コミュニティ”の形成が非常に効果的だと思います。テーマに関心を持つ人を集め、運営を得意とする人に任せると、自然と活発な議論や情報交換が生まれる。コミュニティを育てること自体が、企業風土を変革していく大きな推進力になりますね。

朝比奈
企業風土を改革するキーパーソンは誰だとお考えでしょうか?
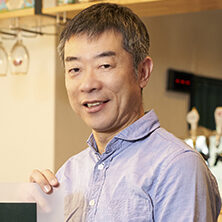
三枝
革新的な役割を担うのはマネジャー層だと考えています。実際にリスクを取って「挑戦してみよう」と導けるのは、現場を統括するマネジャーにほかなりません。こうした判断力や度量をマネジャーに育むことも、企業風土の改革には不可欠な要素です。

朝比奈
なるほど……たしかにそうですね。ミドルマネジメントが現場と経営方針を繋ぎ、挑戦意欲のある人材を後押しする体制があってこそ、大きな変化が実現する。トップダウンとボトムアップが有機的に連携することで、全社的なDXが前進するのだと実感しています。


朝比奈
小さな成功体験を積み重ねることで、現場が自ら「やってみよう」と動き出す場面を作れると、企業風土そのものが変わりやすいですよね。ただ、思うように進展しないケースもあります。そういった時に、現場を巻き込むためにどのような取り組みが効果的でしょうか?
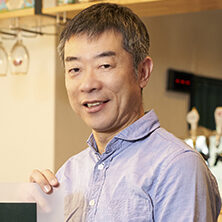
三枝
まずは小規模なプロジェクトを立ち上げ、現場と協働して具体的な成果を上げることが大切です。その成果を担当者の言葉で社内に発信していく仕組みを作ることで、「我々チャレンジしてみよう」という意識が広がり、活用への関心が高まります。
私自身、CDOとしてDXを推進する際、全体の8割近くの時間を組織面の調整や現場とのコミュニケーションに費やしてきました。当初は「こんなツールは使えない」と拒絶されることもありましたが、本質的な課題を解決するための議論に時間をかけて理解を深めるうちに受け入れてもらえるようになるんです。こうした地道な積み重ねこそが、DXを本当に根付かせるための現実的なアプローチだと感じています。

朝比奈
なるほど。おっしゃる通り、最初の段階は特に進みにくいケースが多いかと思います。DXの責任者が現場と連携する時に意識すべきことは何でしょうか?
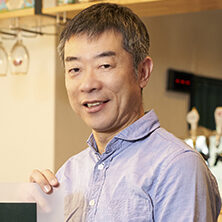
三枝
日本企業には従来のプロセスやルールが深く根付いており、「標準から外れることは許容されない」という風土が色濃く残っているケースが少なくありません。
そこで重要となるのが、“ファーストペンギン”として最初に行動を起こす部署や個人を見いだすことです。先行して成功事例を積み重ねることで、「これは本当に使えるかも」と他部署も前向きに検討するようになり、結果として組織全体の動きが加速していく。だからこそ、現場の価値観を尊重しながら、新しい方法をともにつくり上げていく姿勢が大切ですね。

朝比奈
成功体験を積み重ねながら、都度アップデートするのは本当に難しいと実感しています。そのためにも、現場との対話を絶やさず、制度やルールを柔軟に調整することで、初めてDXが本質的に組織へ根付いていくのだと感じます。三枝さんから見て、パーソルグループ全体へDXをさらに浸透させるには、どのようなポイントが重要でしょうか?
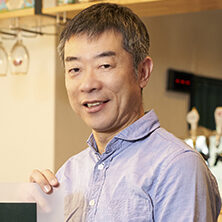
三枝
「はたらいて、笑おう。」というグループビジョンはとても素晴らしく、「テクノロジードリブンの人材サービス企業」という方向性も明快です。ただ、従業員規模が大きい組織では、そうした方針を自分の職務にどう結びつければいいかが見えにくい場合もあります。
そこで重要になるのが、ミドルマネジャーによる“翻訳”です。例えば、テクノロジー部門であれば「テクノロジー活用」のイメージはしやすいかもしれませんが、他の部門ではピンとこないこともあり得ます。そうした部署に対して「具体的にどのように活用できるか」を示していくと、一人ひとりが自分の業務に置き換えられるようになり、一気に広がっていくと思います。


朝比奈
DXを進めていく際、コミュニティメンバーやミドルマネジャーなど、周囲の力を借りて進める大切さを改めて感じました。では、DX推進のリーダーはどんなスキルやマインドセットを持つとよいでしょうか?
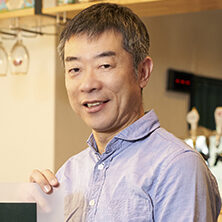
三枝
自社の現状を冷静に分析し、失敗を許容しながら小さな実証を素早く繰り返す思考力、そして周囲の抵抗を和らげつつ協力を得るコミュニケーション力の両方が必要だと思います。私が経営幹部に繰り返し説明していたのは、「どれほど緻密な設計図も、計画どおりに進むとは限らない」ということです。特に企業規模が大きいほど、「Fail small learn fast(小さく失敗し、素早く学ぶ)」という考え方を根付かせるアプローチが重要だと考えます。
加えて、組織のビジョンを常に意識する姿勢も欠かせません。パーソルグループの「はたらいて、笑おう。」であれば、「どうすれば、すべての社員が笑顔ではたらけるか」を問い続けることで、DX施策も自然とその目標に沿った方向性を帯びていくはずです。

朝比奈
ありがとうございます。ここからの取り組みはまさに終わりのない挑戦だと思います。社員が笑っていないなら、まだ道半ばですからね。DXはデジタルテクノロジーだけに注目しても進みにくく、必要に応じて古い規定やルールを見直していく必要があります。ただ、一度に大きく変えるのは難しいので、一つひとつ段階的な改善を積み重ねるしかありません。そうした地道で多角的なアプローチを続ける意志と粘り強さこそ、DX責任者に求められる資質なのだと私も感じています。

朝比奈
ここまでDX推進における数々のポイントを伺い、とても勉強になりました。挑戦を繰り返してこられた三枝さんが考える、「DX推進を担う際の大きな魅力や楽しさ」とは、具体的にどんなところにあるのでしょうか?
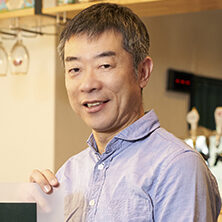
三枝
最大の魅力は、「前例にとらわれず、新しい挑戦ができる」という点です。通常の部署では失敗がマイナス評価に繋がりがちですが、DX推進の部署は「成功するかどうかは未知数」という前提で取り組めます。私自身、「まず小さく試し、うまくいかなければ迅速に別の方法を探す」というアプローチを実践してきました。成功すれば大きな成果を生み出し、失敗しても次の挑戦への糧となる。そのサイクルを重ねるうちに、想像もしなかった競争力が生まれるんです。
これからDX推進を担う方々には、「失敗を恐れず挑戦できることは貴重な環境だ」と認識してほしいですね。組織を根本から変革できる可能性を秘めた、これほど刺激的な職務は他にないと確信しています。

朝比奈
私も「失敗を学びに変えられる」点がDXの面白さだと思います。最初はうまくいかなくても、成果を出した時にはチーム全体で達成感を分かち合える。だからこそ、一人で抱えず、協力者を見いだして周囲と連携しながら前進することが大切です。DXは企業文化や経営そのものの変革でもあるので、「もっと良くしたい」と純粋に思える方こそ、ぜひ挑戦してほしいですね。
最後に、三枝さんが考えるDX推進の要諦を教えてください。
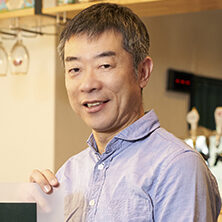
三枝
「はたらいて、笑おう。」にもあるように、まずは楽しむことが大切です。最初から「失敗して当たり前」と考えていれば、うまくいけば大きな喜びが得られ、失敗しても想定内として受け止められます。そうした強いメンタルを持つためにも、「こうやったら面白いんじゃないか」という視点で楽しみを見つけるのが一番だと思いますね。

取材=伊藤秋廣(エーアイプロダクション)/文=嶋田純一/撮影=Palm Tree
撮影場所協力:Aoyuzu by クールスプリングス株式会社
※所属組織および取材内容は2025年5月時点の情報です。
※略歴内の情報は2025年4月時点での内容です。
1

STRATEGY
【後編】未来の“はたらく”を変革する——パーソルホールディングス×パーソルクロステクノロジー 両本部長が語る、AI戦略と共創の最前線
2

PROJECT
わずか10カ月で開発・導入を実現。データドリブンなタレントマネジメント基盤を形にした舞台裏
3

PROJECT
課題の本質をとらえ、伴走型の支援を―コンサルティング×テクノロジーで拓く、地域共創の最前線
4

PROJECT
生成AIによって「女性のはたらき方」が変わり始めた―クラフター小島氏×パーソルテンプスタッフ朝比奈対談
5
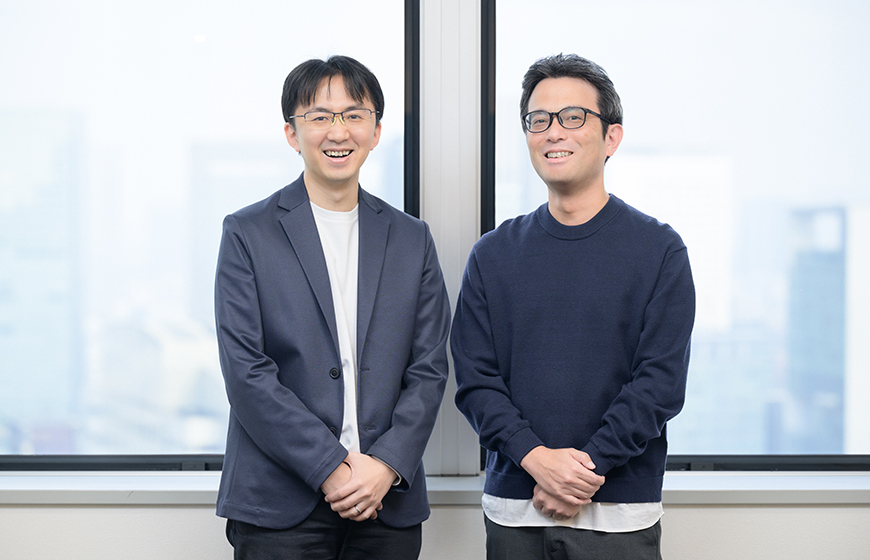
PROJECT
30を超える基幹システムを“無風”でクラウドに。パーソルテンプスタッフが挑むアプリリフト